MSFアンケート結果を発表——紛争地での援助活動は?
2015年04月10日国境なき医師団(MSF)日本では、2015年2月26日~4月3日にかけ、「国境なき医師団の活動について」のアンケートを行いました。質問と回答結果は下記のとおりです。
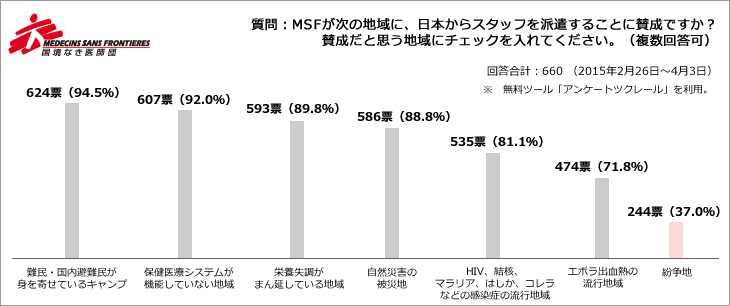
質問で「日本からの派遣に」と限定したのは、どこか遠い国についての出来事ではなく、日本社会の中で生活している一人一人に関係があることとして考えていただきたかったからです。
ご覧のとおり、日本から派遣することに「賛成」と投票された方が最も少なかったのは「紛争地」でした。同時に、自由回答欄にはさまざまなご意見が寄せられました。特に多く寄せられたご意見を5つにまとめました。
※ 主旨を変えない範囲で編集しています。
紛争地に日本からMSFスタッフを派遣することに賛成ですか?反対ですか?
- 紛争地は危険すぎる
「医療を提供する前に命が危険にさらされる可能性が高いから」 - 危険を避けることでより多くの命を救える
「紛争地ではスタッフが拉致・負傷・死亡するリスクが高く、その場合、助けられたはずの命が助けられなくなってしまう可能性があり、見極めが重要」 - 回答が難しい
「世界中くまなく医療をとどけることには賛成ではあるのです。でも危険を冒してまで紛争地へ派遣してよいものかどうか、回答は難しいです」 - MSF/スタッフの判断を尊重
「全てに医療が必要なことは当然ですが、スタッフが命を懸けることになるかもしれない現場に行くことを、第三者が賛成、反対と決めることはできません。それを決めた人の気持ちを尊重したいと考えています」 - 必要とされる場所に行ってほしい
「必要とされる場所には派遣して欲しいと思います。紛争地や自然災害の被災地では安全の確保が難しい場合もあるでしょうが、手を尽くして欲しいと思います」
MSFは紛争地でどのように活動しているのでしょうか?
私たちMSFのスタッフも、皆さまと同じ疑問やジレンマを感じながら活動を続けています。それでも救えるはずの命を救うため……
MSF独自の安全基準に従い、活動の開始・継続・停止を判断しています。

医療ニーズ、必要な活動、治安状況等を把握するため現地調査や日々のモニタリングを行い、安全基準に基づいて判断を下します。
その結果、
- 活動を停止して一時避難し、状況を見て再開する
- 活動地域を縮小する(シリアなど)
- 完全撤退する(ソマリアなど)
というように、医療を切望する人びとがいるとわかっていても、苦渋の決断を行う場合もあります。
「独立・中立」を堅持するMSFだからこそ、紛争地であっても活動できる場所があります。

MSFの医療・人道援助の現場には、敵も味方もありません。政治・宗教・人種・思想などの関わりを超えて差別することなく行動しています。
その理念を貫くため、活動資金の9割を民間からの寄付でまかなっています。
参考情報:国境なき医師団の「憲章」
活動地では、市民、行政、武装勢力に至るまですべての当事者に活動の意図を説明しています。さらに、患者・家族、スタッフ、医療施設の安全を確保するため、施設の敷地内への「武器持ち込み禁止」を徹底しています。
MSFの援助を待っている人びとがいます——シリアの場合
2011年の「アラブの春」に端を発する混乱は紛争へと激化し、解決の兆しがまったく見えていません。既に何十万人もの人びとが命を落とし、国民の半数が国内避難民・難民となって、世界で最も人道危機が深刻な場所と言われます。
ヘリコプターから塩素ガスが詰められたタル爆弾が投下された。病院に運び込まれた多数の負傷者の中に、夫婦と幼児3人の一家も。全員が重度の呼吸困難でまもなく亡くなった。子どもたちの祖母は病院へ搬送することさえできなかった。(2015年)
ルカヤさん(14歳)はお母さんと一緒に出かけるところだった。「家を出た途端、爆発音がしました。両脚が無くなったような気がして、そのまま意識を失いました。気づいたら病院で、お母さんは亡くなっていました」(2014年)
MSFには何ができて、何ができないか——。
厳しい現実と向き合いながら、私たちは今後もできることを考え続けます。皆さまのご意見も、引き続きお聞かせください。
messageboard@tokyo.msf.org参考情報:ノーベル平和賞の受賞記念スピーチ……「ウメラ、ウメラシャ!(勇気を出して!)」
MSFは1999年、その活動方針と活動実績により、ノーベル平和賞を受賞しました。受賞記念スピーチでは、紛争地での活動に対するMSFの考え方について、事例を交えてお話しています。長文ですが、ぜひご覧ください。











