コンゴ民主共和国:佐世保の空襲を生き延び、紛争地で命をつないだ83歳の外科医──いまの日本に伝えたい一つのこと
2025年08月04日
アフリカ中部・コンゴ民主共和国(以下、コンゴ)では、豊かな天然資源を巡る争いなどが絶えない。2025年1月には北キブ州などで政府軍や武装勢力「3月23日運動(M23)/コンゴ川同盟(AFC)」の間で戦闘が激化。大勢の人びとが避難を余儀なくされた。
外科医の菅村洋治(83)は2007年に長崎県佐世保市の病院を定年退職した後、国境なき医師団(MSF)に参加。外科医としてコンゴなどに派遣され、紛争の現実を目の当たりにしてきた。
自身も、かつて日本の戦争を体験した。佐世保市で空襲に遭い、終戦後の苦しい日々を生き抜いた。「人は80年たっても同じことを繰り返している」と話す菅村。国内外で命と向き合ってきた医師として、現在の日本に伝えたいことが一つあるという。
外科医の菅村洋治(83)は2007年に長崎県佐世保市の病院を定年退職した後、国境なき医師団(MSF)に参加。外科医としてコンゴなどに派遣され、紛争の現実を目の当たりにしてきた。
自身も、かつて日本の戦争を体験した。佐世保市で空襲に遭い、終戦後の苦しい日々を生き抜いた。「人は80年たっても同じことを繰り返している」と話す菅村。国内外で命と向き合ってきた医師として、現在の日本に伝えたいことが一つあるという。
菅村洋治(すがむら・ようじ)
1942年、長崎県佐世保市生まれ。新潟大医学部卒業。2007年に佐世保中央病院を定年退職した後、国境なき医師団に参加。ナイジェリア、イラン、コンゴ民主共和国などに派遣された。現在は同病院の非常勤医を続けている。
停電の手術室に響いた産声
──コンゴに派遣された際、どのような活動をしましたか。
2008年6月、北キブ州のルチュルという地域にある病院に外科医として派遣されました。
病院には、紛争による国内避難民をはじめ、さまざまな地域から患者さんが訪れていました。この地域で唯一、外科治療をしている病院だったのです。
たくさんの手術をしましたが、銃撃などを受けて負傷した人の治療や、妊娠した女性の帝王切開が多かったです。現地の出産は、妊娠中のケアが十分にできないなどの理由で早産や低体重児が多かったです。
病院には、紛争による国内避難民をはじめ、さまざまな地域から患者さんが訪れていました。この地域で唯一、外科治療をしている病院だったのです。
たくさんの手術をしましたが、銃撃などを受けて負傷した人の治療や、妊娠した女性の帝王切開が多かったです。現地の出産は、妊娠中のケアが十分にできないなどの理由で早産や低体重児が多かったです。

私が担当しただけでも、わずか2週間で23人の赤ちゃんが帝王切開で生まれました。中には私の名前から取って「YOJI」と名付けられた子もいるんですよ。
ただ医療設備は不十分で、胎児の体位などを確認する超音波装置もありませんでした。
ただ医療設備は不十分で、胎児の体位などを確認する超音波装置もありませんでした。
──印象的な出来事はありましたか。
ある激しい嵐の夜のこと。私がいつものように帝王切開を始めようとした際、手術室が停電しました。
時間は午後11時ごろ。非常灯もつかず辺りは真っ暗で、私はどうしたものかと考えながらじっとしていました。隣にあるもう一つの手術室では、帝王切開の真っ最中でした。
5分ほどたったでしょうか。大丈夫かと心配していた、その時でした。
「おぎゃー!おぎゃー!」
元気いっぱいの赤ちゃんの産声が、隣の手術室から聞こえてきたのです。両方の部屋からスタッフの歓声が上がりました。

停電して手術を続けられるかさえ分からない逆境の中、簡易ライトの明かりだけで生まれてくる生命力の強さに感銘を受けました。
私はこれまで数々の活動地を訪れましたが、あのときの出来事はいま思い出しても涙が出てくるほど最も印象に残っています。
私はこれまで数々の活動地を訪れましたが、あのときの出来事はいま思い出しても涙が出てくるほど最も印象に残っています。
コンゴから途絶えたメール
──コンゴでは2025年1月、戦闘が激化しました。北キブ州も戦闘地域の一つです。
私の派遣期間中、フランス語の通訳を担当してくれた地元のコンゴ人の男性がいました。
寝食をずっと共にする中で、寝る前にはお互いの身の上話をする仲になりました。当時32歳だった彼の夢は、外交官になることでした。
私がコンゴから帰国した後も、年に4、5回は数行のメールを送り合い、近況報告をしていました。
彼はルチュルの家をゲリラに追われてしまい、同じ北キブ州にある州都ゴマの避難民キャンプに身を寄せていたそうです。そこで結婚し、子どももできて、新しい生活を送っていたと聞いていました。
寝食をずっと共にする中で、寝る前にはお互いの身の上話をする仲になりました。当時32歳だった彼の夢は、外交官になることでした。
私がコンゴから帰国した後も、年に4、5回は数行のメールを送り合い、近況報告をしていました。
彼はルチュルの家をゲリラに追われてしまい、同じ北キブ州にある州都ゴマの避難民キャンプに身を寄せていたそうです。そこで結婚し、子どももできて、新しい生活を送っていたと聞いていました。

そのゴマで戦闘が激化したことを知り、彼のことが気になって「元気ですか」とメールを送ってみました。しかしいまだに返信がありません。
最後に連絡がついたのは半年前のこと。毎日、彼の無事を心配しています。
防空壕に逃げ込んだ夜
──日本では、終戦間近に佐世保空襲を体験していますね。
あれは1945年6月28日の深夜でした。
突然、米軍のB29爆撃機が飛んできて「ウーウー」というサイレンが鳴り始めました。近所にある町の公会堂からは「空襲警報発令!空襲警報発令!」という叫び声が聞こえてきました。
佐世保には軍港があるから狙われたのでしょう。間もなく至るところに焼夷(しょうい)弾が落ちて、花火みたいにパッパッパッと火花を上げていたことを覚えています。
当時、3歳半だった私はわけもわからないまま、一緒に暮らしていた親戚たちと防空壕(ごう)に隠れました。自宅の玄関先に掘っていた「く」の字形の穴で、両親、きょうだい、いとこ、おじ、おばら計10人以上が身を寄せ合いました。
2階建ての自宅にも焼夷弾が落ちましたが、父親はトタン板を上からかぶせるなどして必死に消し止めていました。しばらくして父親が叫びました。
突然、米軍のB29爆撃機が飛んできて「ウーウー」というサイレンが鳴り始めました。近所にある町の公会堂からは「空襲警報発令!空襲警報発令!」という叫び声が聞こえてきました。
佐世保には軍港があるから狙われたのでしょう。間もなく至るところに焼夷(しょうい)弾が落ちて、花火みたいにパッパッパッと火花を上げていたことを覚えています。
当時、3歳半だった私はわけもわからないまま、一緒に暮らしていた親戚たちと防空壕(ごう)に隠れました。自宅の玄関先に掘っていた「く」の字形の穴で、両親、きょうだい、いとこ、おじ、おばら計10人以上が身を寄せ合いました。
2階建ての自宅にも焼夷弾が落ちましたが、父親はトタン板を上からかぶせるなどして必死に消し止めていました。しばらくして父親が叫びました。
「ここも危ないから出てこい!」
みんなが散らばり、私は臨月だった母親と共に兵舎の防空壕に飛び込みました。後になって、他のきょうだい4人は20~30メートル離れた別の防空壕に逃げたと聞きました。
生きるか死ぬかの事態で、まとまって同じ方向に逃げる余裕すらなかったのです。
生きるか死ぬかの事態で、まとまって同じ方向に逃げる余裕すらなかったのです。
──空襲がやんだ後、周辺はどのような状況でしたか。
結局、空襲は翌29日の未明にかけて続きました。
それまでも空襲はありましたが規模がまるで違いました。周辺で建物が焼けずに残ったのはうちだけでした。
それまでも空襲はありましたが規模がまるで違いました。周辺で建物が焼けずに残ったのはうちだけでした。
隣の家には老夫婦が住んでいましたが、おじいちゃんは縦穴式の防空壕で座ったまま焼け死んでいたそうです。
自宅でも、焼夷弾のうち1発が、外に避難した直後の母親の枕を貫通していました。板張りの廊下には焼け跡が残り、凹凸に黒光りしていました。
余談ですが、いまは亡き父は晩年、辺りが台風で停電した際に「空襲警報発令!空襲警報発令!」と言って廊下に飛び出したそうです。それほどまでに空襲の体験が、父の記憶に深く刻まれていたのだと思います。
余談ですが、いまは亡き父は晩年、辺りが台風で停電した際に「空襲警報発令!空襲警報発令!」と言って廊下に飛び出したそうです。それほどまでに空襲の体験が、父の記憶に深く刻まれていたのだと思います。
日本だから、できること
──戦後はどんな暮らしでしたか。
街は焼き尽くされ、道が広くなっていました。とにかく物がない時代で、小学校には素足で通学していました。
もちろん食べるものもない。そこら辺にいるイナゴを捕まえて、焼いて食べていました。当時は貴重なたんぱく源です。給食も量が少なく、わずかな乾パンと粉ミルクのようなものだけでした。
街には進駐軍の外国人が行き交っていました。いつも空腹だった私たちが食べ物をねだると、彼らはチョコやキャラメル、チューインガムを投げ与えてきました。
もちろん食べるものもない。そこら辺にいるイナゴを捕まえて、焼いて食べていました。当時は貴重なたんぱく源です。給食も量が少なく、わずかな乾パンと粉ミルクのようなものだけでした。
街には進駐軍の外国人が行き交っていました。いつも空腹だった私たちが食べ物をねだると、彼らはチョコやキャラメル、チューインガムを投げ与えてきました。
道端では少女が花を売り、少年が「10(てん)円!10(てん)円!」と声をかけながら米兵たちの靴を磨いていました。
小学6年生のとき、修学旅行で長崎市を訪れました。市内には米軍に原爆を投下された爪痕がまだ強く残っていました。
爆心地からほど近い旧浦上天主堂は、当時まだ廃虚の状態。そのとき、戦争が残した影響の大きさを子どもながらに強く感じたことを覚えています。
爆心地からほど近い旧浦上天主堂は、当時まだ廃虚の状態。そのとき、戦争が残した影響の大きさを子どもながらに強く感じたことを覚えています。
──今年で終戦から80年。現在の日本社会に伝えたいことはありますか。
近年の海外ニュースは戦争の話ばかりです。紛争地の人びとがあの恐ろしい空襲警報におびえ、食べるものさえない日々を送っているかと思うと、胸が痛くなります。
「人は80年たってもまだ同じことを繰り返している」と悲しい気持ちになるのです。
日本ではもう80年間も空襲はありませんが、今の若い人たちにはこの状況を当たり前だと思わないでほしい。そして、こんなに平和で良い国はないということを知ってほしいです。
私は小学校で話す機会があると、「君たちは日本に生まれただけで、1億円の宝くじに当たったぐらい幸運なんだよ」と必ず言うようにしています。
私は小学校で話す機会があると、「君たちは日本に生まれただけで、1億円の宝くじに当たったぐらい幸運なんだよ」と必ず言うようにしています。
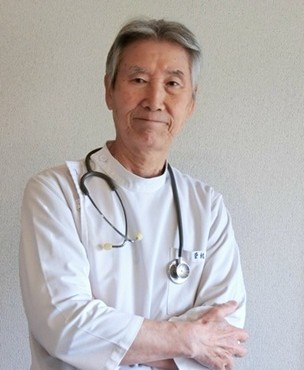
平和の大切さを教育で後世に伝えていくことが、とても大切だと思います。同時に、戦争を直接体験した人たちが年々亡くなってしまい、その悲惨さがますます分かりづらくなってしまうのではないかと危惧しています。
社会では最近、「自分のことだけを考えればいい」という風潮がありますね。しかし世界というのは、何かが変わってから急いで対処しようとしても取り返しのつかない状況になります。
内にこもっていてはいけません。自分のことはしっかりとしつつ、同時に世界と助け合う気構えが必要です。
社会では最近、「自分のことだけを考えればいい」という風潮がありますね。しかし世界というのは、何かが変わってから急いで対処しようとしても取り返しのつかない状況になります。
内にこもっていてはいけません。自分のことはしっかりとしつつ、同時に世界と助け合う気構えが必要です。
痛ましい戦争を経験した日本だからこそ、この世界でできる援助がある。 いまの若い人たちに、私はそのことを伝えたいです。











