海外派遣スタッフ体験談
自分の経験を現場に活かし、現地医師に伝授
城倉 雅次
- ポジション
- 整形外科医
- 派遣国
- アフガニスタン
- 活動地域
- クンドゥーズ
- 派遣期間
- 2014年3月~2014年6月

- Q国境なき医師団(MSF)の海外派遣に再び参加しようと思ったのはなぜですか?また、今回の派遣を考えたタイミングはいつですか?
-
職場に退職する意向を伝えたあとです。退職の意向は3ヵ月前に示していたので、それから派遣先を探してもらっても、予防接種も含めて十分間に合いました。
自分としては、パレスチナの形成再建プログラムを希望していましたが、MSFでは活動地のニーズによって派遣先が決まりますので、結局、アフガニスタンとなりました。
MSFがアフガニスタンで運営するクンドゥーズ外傷センターが昨年から本格的に稼働しており、私の派遣以前にもMSFではベテランの日本人整形外科医が2名、すでに派遣されています。
- Q派遣までの間、どのように過ごしましたか? どのような準備をしましたか?
-
準備は特に何もしていません。英語は直前にジタバタ特訓しても意味が無いと分かっているので、今回は何もしませんでした。その代わり、ちょっとかじっていたアラビア語の延長で、ペルシャ語をほんの少しだけ勉強しました。
アフガニスタン北部のクンドゥーズでは、ダリー語が中心に使われていましたが、ほとんどペルシャ語(ファルシー)と同じなので、これはかなり役に立ちました。
アラビア文字の基本的な読み書きが出来ることも、スタッフとのコミュニケーションの上で、大変大きなメリットがあったと思います。やはり、現地の人が普段使っている言語を少しでも勉強していけば、どこの国へ行くにしても役に立つと思います。
- Q過去の派遣経験は、今回の活動にどのように活かせましたか? どのような経験が役に立ちましたか?
-
疾患構成としては、外傷センターですから、急性期外傷の治療が圧倒的に多いのですが、アフガニスタンの現地整形外科医が約10名おり、手分けして手術が出来たので、外傷後の2次再建術をやる機会も多くありました。
過去に参加したナイジェリアでの活動で携わった重度外傷初期治療と、スリランカでの活動で行った2次再建治療、両方を合わせたような、多岐にわたる手術でした。手術症例数は9週間で180以上でした。
2次再建治療には、大学形成外科に数年在籍していた時に、先天異常手に対する再建術をいろいろ経験していたのが、今回役立ちました。また、難治性感染症例には、自分の今までの活動での感染治療経験から、MSFの現場に応用できる持続還流法を洗練させ、現地スタッフに伝授しようと努めました。
- Q今回参加した海外派遣はどのようなプログラムですか?また、具体的にどのような業務をしていたのですか?
-
 5月、陽光に包まれるクンドゥーズ外傷センター
5月、陽光に包まれるクンドゥーズ外傷センター
日本でもまだ少ない外傷治療専門のセンターです。病床数は75床くらいです。手術室は3室中、2室が稼働していました。
運ばれてきた重症外傷患者さんは、救急でトリアージされ、蘇生室で応急処置後、必要なら手術室へ搬送、ICU管理と、よくシステム化されていました。
病院は1階建てで、フロアにはER、手術室のほか、一般整形外来、ギプス室、処置室、理学療法室、心理療法室、レントゲン室、カルテ室などがあり、別棟で敷地内に、女性病棟を含む4つの一般病棟・感染患者用隔離病棟、スタッフ・オフィス、厨房、ミーティング・ルームなどがあります。敷地面積だけでもかなり広く、今も拡張が続いています。
クンドゥーズはアフガニスタン北部のタジキスタン国境に近い州で、近隣地域、時には市内からも、爆弾・銃による負傷者が毎日のように運ばれて来ました。
銃外傷は、ナイジェリアでたくさん経験ずみでしたが、爆弾外傷は、被弾間もない状態で見るのは実は初めてで、衝撃的でした。その同時多発的、壊滅的な組織損傷(消滅といっても言い)には絶句でした。体幹部損傷を合併していることが多く、外科医の開腹手術との同時手術になることも多かったですが、四肢損傷を頑張って治療しても、腹部外傷や大血管損傷による失血で亡くなられる患者さんが後を絶ちませんでした。
現地に到着したのは治安が不安定な時期で、爆弾外傷の患者さんが非常に多く、着いたその日からすぐに手術に入らなければなりませんでした。選挙前後は病院へ泊まり込み、以後9週間休む間もなく働き続けました。
 整形外科、外科、麻酔科の手術室チーム
整形外科、外科、麻酔科の手術室チーム
海外派遣スタッフは、医療統括担当の医師が1名、整形外科医2名、一般外科医1名、ER/ICU医1名、麻酔科医が2名おり、看護師は看護統括担当が1名、病棟、手術室、ER/ICU、外来に各1名、これに理学療法士1名、心理療法士1名、薬剤師1名を加え、医療スタッフが15名です。
アフガニスタンの現地スタッフは、整形外科医、外科医が監督医を含めて11名、麻酔科医が4~5名、これに理学療法スタッフ、心理療法スタッフ、病棟・手術室スタッフ数十人が加わりますので、すごい数です。とても全員名前を覚えられませんでした。
とにかく、今まで参加したMSFの活動に比べて、医療スタッフの数は圧倒的に多かったです。ここにさらに、非医療スタッフも加わります。毎朝7時45分から全体ミーティングがあるのですが、毎日部屋一杯で入りきれないほどでした。
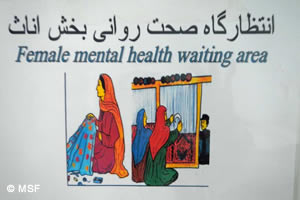 心理療法待合室のサイン
心理療法待合室のサイン
今までの活動と違って印象深かったのは、理学療法もそうですが、心理ケアにも大きな力が注がれていることでした。特に、銃や爆弾外傷を受けて入院した患者さんは、翌日には心理療法士のカウンセリングを受ける体制が出来ていました。
体の一部を外傷で失った患者さんや、四肢を切断する手術が予定されている患者さんにもカウンセリングがありました。日本の外傷センターでそこまでの体制ができている所は無いのでは、と思います。
- Q派遣先ではどんな勤務スケジュールでしたか?また、勤務外の時間はどのように過ごしましたか?
-
私が赴任するまで、海外からの整形外科医の派遣は途切れていました。現地では私の到着を待ちに待っていたようです。本来は海外派遣スタッフの整形外科医は2人体制のはずなのですが、私以外どこの国からも派遣が無く、派遣期間の9週間のほとんどを、1人で病棟回診も手術も行いながら、外来からの頻回のコンサルトにも対応しなければならず、多忙を極めました。当然、オンコールも毎日でした。
午前中は病棟を回診する日と手術に入る日をなるべく交互にして、病棟回診で患者さんの状況を把握したかったのですが、手術スケジュールの調整が困難で、緊急手術で呼ばれることも多く、患者さんの全体像を常に把握しているのは不可能でした。
毎日、多い時で6~7名の手術をしていました。治安上、海外派遣スタッフの屋外移動は厳しく制限され、決められた時間に車に乗って病院と宿舎を往復する毎日です。
昼は12時半から1時半まで宿舎に帰って昼食をとるのですが、車の出発時間に手術が終わらず、1時間後にスタッフが運んで来てくれるランチ・ボックスで済ませたことも何回かありました。
また夕方は18時半が車の最終なのですが、それに間に合わないこともしょっちゅうで、そうなると、夜は誰もいないダイニングで寂しく食事することになります。時には食事さえめんどうくさく、部屋に戻れば疲労感で寝てしまう毎日でした。今回は本当によく寝ました。
イスラム教国のアフガニスタンは金曜が休日で、ちょうど欧米や日本の日曜日にあたります。木・金は外来も無く病院内も静かで、週末という雰囲気でした。
金曜は定期手術が無く、緊急手術のみなので、唯一午前中にゆっくり回診出来る日でした。整形外科が2人いれば交代で朝から休んでもいい日なのですが、1人だったので、入院患者さんの把握のため、休んではいられませんでした。
金曜の午後になって、待ちに待った唯一の休息の時間が訪れるのですが、緊急手術で休日返上になることが多く、結局本当に休めたのは2日程度でした。
- Q現地での住居環境についておしえてください。
-
病院から車で10分くらいのところにある、立派な4階建ての2棟の集合住宅です。全部で25室はあったと思いますが、スタッフの数が多く、首都のカブールからも入れ替わり人が来るので、いつも満室に近かったです。
ダイニングも食事の時は人であふれていました。フロア毎にトイレ、ホット・シャワーがあり、部屋もエアコン付きでまあ快適でしたが、部屋によって広さ、明るさにだいぶ差がありました。
地下にはフィットネスのマシーンもあり、結構皆運動していました。何しろ、休日でも全く塀の外に出られないのですから。屋上では、星空の元、バーベキューや映画上映会がよく開催されていました。
- Q活動中、印象に残っていることを教えてください。
-
着任当初は、同じく日本から派遣されたER/ICU医の先生がおられ、5週間一緒に仕事をしました。また最後の数日は、私の後任として赴任された整形外科医の先生と少し一緒に仕事ができました。期間限定でしたけれども、日本語で話せる仲間がいたのは、とても良かったです。
アフガニスタンの整形外科の指導医クラスのレベルは標準以上で、良く勉強されていました。通常の骨折治療なら新しく教えることは特に無いばかりか、逆に私たちの方が、普段高価なインプラントや便利な機器に囲まれて手術をしているので、限られた機器しか使用出来ない環境では、むしろ教えられることもあります。
現地整形外科医の、MSFの海外派遣スタッフが行う手術への要求度は大変高く、骨折の整復が少しでも不十分だとやり直しを求められ、術後X線写真でスクリューが少しでも長く出ていると指摘されます。常にプレッシャーを感じて手術をしていました。
そもそも、海外派遣スタッフが担当するのは、いろいろ問題のある骨折なので、それだけでも難易度が高いのですが。
ただ、彼らにとってはまだ「外傷=骨折」の域を抜け出しておらず、レントゲン上の異常を直すことに躍起になっている段階でしたので、合併する筋腱・神経の修復も同じくらい重要なことを、自分の手術治療を通して少しずつ理解してもらおうとしました。
神経の重要性は、頸部を銃弾が貫通して上肢麻痺をきたした10歳の男児に、頸部を展開し腕神経叢損傷を確認して多数神経移植を行った手術が大きなインパクトを与えたのもあって、以後、神経麻痺症例のコンサルトは多くなりました。
筋腱の再建は、毎週1回ある朝のレクチャーで、神経麻痺手の腱移行による再建法をテーマに講義しましたが、実際の手術を示すには少し時間が足りませんでした。
もうひとつ、手を損傷して親指が切断された若者に、血流と感覚のある人指し指を親指にする「示指の母指化術」をやったのが、現地医師には衝撃的だったようです。いろいろな手術の可能性を示すには、いい症例だったかもしれません。このほかにも、下腿の皮弁の移行術や、感染創の持続還流法など、比較的易しく役に立つ方法を、積極的にアフガニスタンの先生たちに伝授するよう努めました。
- Q今後の展望は?
-
また就職しますので、しばらく参加はできません。定年後には、毎年参加したいと思います。今は、日本からアフガニスタンの先生たちをサポートできる方法を考えます。
- Q今後海外派遣を希望する方々に一言アドバイス
-
現地で使用しなければならない髄内釘や創外固定器などは日本では見たことも無い特殊でクセのある代物です。日本では当たり前に使える道具もありません。結果、原始的ともいえるやり方で手術をやらねばならない事も多くあります。
でも、基本は同じです。少しの頭の転換と慣れでなんとかできます。この経験は、必ず自分の人生の糧になると思います。たとえ短期でも、一生懸命やりさえすれば、自分にとっても現地にとってもプラスになるはずです。
MSF派遣履歴
- 派遣期間:2010年11月~2011年3月
- 派遣国:スリランカ
- プログラム地域:バブニヤ
- ポジション:整形外科医
- 派遣期間:2009年11月~2010年1月
- 派遣国:ナイジェリア
- プログラム地域:ポートハーコート
- ポジション:整形外科医
- 派遣期間:2009年1月~2009年2月
- 派遣国:ナイジェリア
- プログラム地域:ポートハーコート
- ポジション:整形外科医







