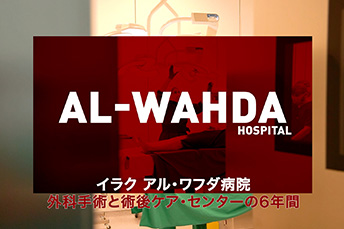命をつなぐ連携の力──イラクで進化する結核対策と日本人スタッフが感じた希望
2025年10月27日
結核と闘った家族の記憶──
ザイナブが結核だと知ったときは、本当にたくさん泣きました。でも、医師が慰めてくれて、『きっと良くなりますよ』と励ましてくれたんです。
ウンム・サラームさん サドルシティの住民
MSFはこれまで、イラクの保健省や国立結核研究所、法務省と連携しながら、国内の結核患者の5分の1が集中するこのサドルシティ地区や、発生率がさらに高い刑事収容施設においても、結核と闘う取り組みを続けてきた。
- ※アバヤ:主にイスラム諸国で女性が着用する、全身を覆う伝統的な衣装。黒いコートのようなデザインが多く、ゆったりした作りで身体のラインを隠すことを目的としている。

制度と偏見──二重の障壁
イラクは近年、結核対策において大きな進展を遂げており、国立結核研究所によれば、発生率は約61%減少した。
それでもなお、子どもや栄養不良に陥っている人びと、糖尿病の管理が不十分な患者、そして喫煙者は、感染リスクが高い状態に置かれている。特にサドルシティ地区は、人口の過密、深刻な貧困、そして医療アクセスの難しさといった要因が重なり、依然として主要なホットスポットとなっている。
こうした社会背景に加え、イラクの医療制度は技術面・財政面の両方で課題を抱えている。例えば、結核の診断に用いられる「GeneXpert」のような最新機器は高価で、継続的なメンテナンスや消耗品の確保が欠かせない。さらに、国際的なルートを通じた医薬品の調達は、煩雑な行政手続きによって、しばしば遅れが生じている。
また、結核に対するスティグマは未だ治療における最大の障壁であり、多くの患者が差別を恐れて病気について口を閉ざし、治療をためらう現状がある。

命を守るための協力体制
MSFは2018年よりイラクで結核プログラムを実施しており、国立結核研究所を支援するとともに、世界保健機関(WHO)の勧告に沿った治療法の更新に取り組んでいる。
MSFがイラクで活動を始めた当初、結核の治療はまだ毎日の注射を基本とした方法が主流だった。この治療法は痛みを伴い、副作用も強く、効果も十分とは言えないものだった。しかし、新しい経口薬が導入されたことで、MSFはより安全で、効果的な治療法の普及を支援できるようになった。
「2019年以前は、薬剤耐性結核の患者やその家族に『命を落とす可能性が非常に高い』と伝えざるを得ませんでした」と、イラク国立結核研究所の副所長であるライス・ガジ医師は話す。
しかし、MSFと協力して最新の治療法を導入してからは、治癒率が90%近くにまで向上しました。今ではイラクは、周辺諸国の中でも結核治療の先進国となっています。
ライス・ガジ医師 イラク国立結核研究所・副所長
MSFは治療だけでなく、「GeneXpert」など最新の診断機器を提供することで、診断体制の強化も行っている。これにより、薬剤耐性の初期検出にかかる時間が、従来の1カ月以上からわずか1日に短縮された。
MSFはまた、WHOのガイドラインに基づき、子どもを対象とした早期発見プログラムも開始した。この取り組みによって、ザイナブちゃんをはじめ、今年は数十人の子どもたちが早期検査を受けた。
さらにこのプログラムは、地域での健康推進活動と組み合わせることで、すでに前向きな変化を生み出し始めている。人びとは検査や治療により積極的に関わるようになり、関心と理解も高まっている。

MSFの活動は地域の保健施設にとどまらず、刑事収容施設にも広がっている。2024年には、法務省および保健省と連携し、複数の刑務所でスクリーニング活動を支援した。
さらに最近では、従来6カ月かかっていた予防治療に代わり、1カ月で完了する短期経口予防治療「1HP TPT」を導入。これは結核患者の濃厚接触者を対象としたもので、治療の継続にかかる負担を軽減し、特に刑事収容施設におけるフォローアップを、より現実的かつ実行可能なものにしている。
「イラクにおけるMSFの活動の特長は、保健当局や司法当局との緊密な連携にあります」と、MSF結核プロジェクト医療コーディネーターのアパルナ・S・アイヤー医師は言う。
この協力体制により、診断と治療の両方が改善され、国内の刑務所で短期予防治療を初めて導入することができました。
アパルナ・S・アイヤー医師 MSF結核プロジェクト医療コーディネーター

資金、スティグマ──残された課題
こうした成果が見られる一方で、結核対策には依然として多くの課題が残されている。
まず、国の結核対策プログラムの予算は年によって変動する可能性があり、資金が不足すればスクリーニングが実施されなかったり、検査用カートリッジが購入できなかったりする事態も起こり得る。その影響は、患者や治療に尽力する医療従事者に直接的に及ぶ。
スティグマもまた、人びとにとって見えない重荷であり、検査の遅れや患者自身の苦悩を引き起こしている。
MSFの活動の核にあるのは、パートナーとの協力を目に見える成果へとつなげることだ。ガジ医師が語ったように、1カ月の短期予防治療は「命を守ること」に他ならない。それは単に治療期間を短縮するだけでなく、人びとにとって医療をより身近なものにし、資源の限られた過密地域でも治療を可能にするという意味も持っている。
協力が命を守る──これは明らかだ。保健省、法務省、国立結核研究所、そしてMSFがともに達成できた取り組みも、例外ではない。医療の専門知識、国家の制度、そして地域社会の意志が結集したときに、何が実現できるのかを示す一つのモデルと言えるだろう。
安定した資金、患者の尊厳を尊重する啓発メッセージ、そして医療の隙間を埋めるプログラムがあれば、イラクにおける結核ケアの水準はさらに高めることができる。MSFはこれからもこのパートナーシップを通じて、地域社会とともに、確かな成果を生み出すことに力を注いでいく。

※住民の名前はプライベート保護のため仮名にしている。
結核のない未来へ──人びとに寄り添う健康推進活動:錦織智子(にしきおり・さとこ)の報告

MSFはここで主に貧困者層のコミュニティと刑務所を対象に、長い間プロジェクトを続けています。
検査から予防へ──家族を守る取り組み
子どもと打ち解けることで、お母さんたちも少しずつ心を開いてくれて、活動への理解と協力が広がっていきました。

刑務所で広げる結核予防の輪

また、ハトの形に切ったカードに自分の夢を書いてもらい、大きな台紙に貼って飾ったんです。「こんなこと、やってくれるかな?」と少し不安もありましたが、みんな「私も書きたい」と積極的に取り組んでくれて、うれしかったですね。
「職業訓練の修了書がもらえますように」「病気を治して元気に家に帰りたい」など具体的で前向きな内容が多く、皆さん希望を持って生きているんだな、ととても感動しました。
もう二度と犯罪なんて起こさず、穏やかに暮らしていってほしいですし、その良いきっかけになったらいいなと心から思いました。
人とつながる、やりがいある活動
また活動に参加して、もっと多くの方とつながっていきたい──そんな思いを強くしています。