終わりが見えない戦争、でも私たちは終わらない──ウクライナ前線近くに生きる人びとの「回復力」
2024年03月05日
2022年2月にロシア軍がウクライナ各地を攻撃し、激しい戦争に発展してから2年。終わりの見えない戦闘が続くウクライナでは、いまも1000万人近くが家を失っており、国内外で避難生活を送っている。
戦闘の前線は1000キロ以上に及び、人びとは絶え間ないミサイルやドローンによる攻撃にさらされている。ウクライナの前線近くで生きる人びとのストーリーを、国境なき医師団(MSF)の活動とともに伝える。
私たちは終わったわけではない
2022年9月、ウクライナ軍がハルキウ地方を部分的に奪還し、そのクピャンスクは戦闘の最前線から脱する。これを受けて、MSFの医療チームは、リュドミラさんたちの住む村に入って医療活動を開始した。
砲撃のせいで、診療所を設置できるような公共施設は残っていなかった。そこで、MSFは、リュドミラさんに自宅を使用できないか打診し、同意を得た。MSFは、彼女の自宅で近隣住民に向けた医療活動にあたることにしたのである。

「MSFで心理療法士をしている人がアドバイスしてくれたんです。それに従って、地域の人たちに、キャンドル瞑想を使った呼吸法というのを教えているんですよ。平穏で調和のとれた気持ちになれるんです。こうやって、75歳になっても人の役に立つことができている。畑仕事やウサギの世話もしていますよ」とリュドミラさんは語る。
リュドミラさんのいう呼吸法とは、ストレスや不安を和らげるためのシンプルなテクニックだ。ウクライナで活動するMSFの移動診療チームは、通常の医療活動にあたるだけでなく、心のケアにも活動範囲を広げている。その一環として、皆が簡単に共有できる呼吸法を伝えてきた。また、MSFチームは、リュドミラさんの住む地域の人びとと連携して、地元で唯一となる診療拠点を再建している。現在では、同国保健省のスタッフたちも戻ってきた。
リュドミラさんが笑顔でこう話す。
「再建された医療センターは、とても現代風で、地域の人たちのあいだでは"美術館"と呼ばれているんです。このセンターができたおかげで、治療も受けられるし、薬も手に入ります」
前線で前向きに生きる人びと

戦時下における心のケア

ワーニャさんは9歳になる。母親であるオレーナさんは、ドネツク州の戦火を逃れた後、2人の子どもを連れて、キロボフラード州の避難民シェルターで1年以上も暮らしている。前線から比較的離れた地域だが、ドローンやミサイルが間近で飛び交っている。ワーニャさんは、砲撃の音を聞くたびに寝られなくなった。MSF心理療法士チームが、避難所の子どもたちに向けて、グループ遊戯療法というものを施すようになると、やがてワーニャさんも平穏を取り戻した。少なくとも、母親のオレーナさんにはそう見えているようだ。ワーニャさんは、再び学校にも行けるようになった。新しい友達もできたようだ。

MSFの医療列車
テチアナさんが足を失ってから10カ月が経った。現在、彼女は、義肢と松葉杖を支えにして、首都キーウで生活を送っている。負傷した当時、テチアナさんはいったん病院に避難したのち、MSFの運用する列車でリビウに運ばれ、そこで義足を着けることになった。

MSFでプロジェクト・コーディネーターを務めるアルビナ・ザルコワは、次のように話す。
「2022年3月から2023年12月にかけて、MSFは医療列車を使って3808人の患者を搬送してきました。そのうち310人は重篤な状態でした。当時、彼らを安全な場所、安全な病院にまで送り届ける上で、医療列車は欠かせないものでした。今では状況が変わって、救急車を活用するようになりました」
現在では、戦況が変わったため、患者は西部に移送されず、東部にとどまることが多い。一方、MSFは15台の救急車を運用して、砲撃で負傷した人びと、慢性疾患にかかっている人びとを前線から遠く離れた医療施設に搬送している。
ウクライナにおける戦争がどれだけ人道的な影響を及ぼしてきたか。国際的関心は薄れている。しかし、前線における戦闘は相変わらず壊滅的だ。2014年から2022年にかけて、1万4000人以上が死亡した。2022年2月以降、この数は倍増し、数十万人が心身を傷つけられ、1000万人近くが避難生活を送っている。










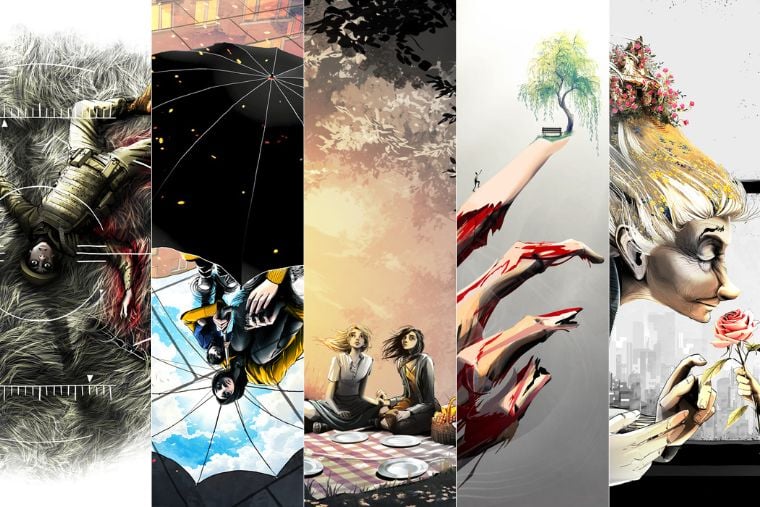

.jpg)