海外派遣スタッフ体験談
5年ぶりの活動参加で新生児医療を援助
岩崎 直哉
- ポジション
- 小児科医
- 派遣国
- ナイジェリア
- 活動地域
- ジガワ州
- 派遣期間
- 2014年9月~2014年10月

- Q国境なき医師団(MSF)の海外派遣に再び参加しようと思ったのはなぜですか?また、今回の派遣を考えたタイミングはいつですか?
-
以前派遣された時の私の写真がMSFのダイレクトメールに使われているのを友人が発見し、私にその事を教えてくれました。この出来事をきっかけに、もう一度MSFの活動地に行ってみたくなって、日本事務局のフィールド人事部に問い合わせをしました。
- Q派遣までの間、どのように過ごしましたか? どのような準備をしましたか?
-
小さな診療所の小児科外来で診療を行っていました。同時に、地域の医師会のメンバーとして小学校の校医を嘱託されたり、夜間急病センターの診療を担当したり、小児救急医療電話相談事業に参加したりと、すっかり地域医療に溶け込んでいました。
約5年前になる最後の派遣から、しばらくは再び活動地に行くことは無いだろうと思っていたのですが、MSFに参加した影響で熱帯医学に興味を持つようになり、長崎大学の熱帯医学研究所で3ヵ月研修しました。
ほかに、熱帯医学に関係の深い渡航医学についても学会に参加して勉強をしていました。自分自身の身を守る事も重要で、熱帯医学や渡航医学の知識はとても役に立ちました。
語学については、英会話教室など特別にレッスンに通うことは無かったのですが、DELFや仏検など、フランス語の資格試験をいくつか受け、レベルを確認しました。
- Q過去の派遣経験は、今回の活動にどのように活かせましたか? どのような経験が役に立ちましたか?
-
活動中の生活環境は、日本での生活とはまったく違うものなのですが、過去の派遣の経験があり戸惑うことはありませんでした。比較的スムーズに現地での生活に順応できました。
限られた医療資源での診療を求められるわけですが、前回の派遣後、日本で診療していても、「もし、この検査や道具が無かったら、その代わりにどうしたらいいだろう?」など、想像を膨らませることがあったので、現地で診療に必要なものが無いことに対する驚きや戸惑いは、今回あまり感じませんでした。ただ、重症例の多さには圧倒されます。
新生児の診療については、小児科医として研修をしていた2年間に、小児医療の一部として新生児医療も経験していました。その後、小児循環器の分野に進みましたが、対象に先天性心疾患がかなり含まれていたので、出生直後から新生児を管理することが常にありました。この点では新生児の専門家に次いで新生児の管理に詳しくなれたのではないかと思っています。
- Q今回参加した海外派遣はどのようなプログラムですか?また、具体的にどのような業務をしていたのですか?
-
 NICU(新生児集中治療室)の様子
NICU(新生児集中治療室)の様子
ナイジェリアのジガワ州で、地方政府が設置している総合病院のなかで、産科関連部門と産科フィスチュラの治療をMSFが援助しているものです。
家庭での分娩が困難な妊婦さんたちが入院して出産(症例によっては帝王切開)する施設です。ここで生まれた赤ちゃんに問題があるときには、新生児室で治療を行います。
私はその新生児室で、小児科医として現地スタッフらと一緒に診療を行うとともに、スタッフのトレーニングなどを行いました。
海外派遣スタッフは短期間で入れ替わることが多かったのですが、常時10名程度でした。病院では、MSFが運営している部門で130名ほどの現地スタッフがいましたが、約半数は政府の保健省から派遣されている職員でした。
産科部門での月あたりの分娩数は約600例です。ほとんどは合併症を伴うため自宅では分娩が困難な症例です。帝王切開も1ヵ月に60~100例あります。新生児の入院は1ヵ月あたり80~100例です。産科フィスチュラでは月平均50例の入院がありました。
- Q派遣先ではどんな勤務スケジュールでしたか?また、勤務外の時間はどのように過ごしましたか?
-
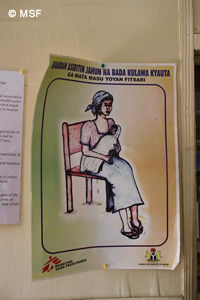 産科フィスチュラのポスターには、
産科フィスチュラのポスターには、
「ジャフン総合病院は無料でケアを提供しています」
と書かれている。朝は8時頃に宿舎を出発し、まず新生児室の回診です。入院患児を一人ずつ診察し、全身状態の評価や治療方針の確認をスタッフとともに行います。回診後は、症例によって長期的な治療方針を話し合ったり、退院の時期を検討したり、時間があるときはMSFのプロトコル(治療手順)の再確認などをしました。
基本的な診療技術(蘇生や機材の使い方など)の再確認も今回派遣された目的の1つだったので、繰り返し行いました。ときには講習会を企画して、休日のスタッフにも参加してもらって、診療の質の改善を図りました。
短期間の滞在で多くのことを期待されたためか、完全な休日はありませんでした。土日の勤務時間をなんとか短縮してもらいましたが、毎日仕事の生活というのは気持ちを入れ替える時間がなく、この事が少しだけつらかったです。
- Q現地での住居環境についておしえてください。
-
 ジャフン総合病院の正門
ジャフン総合病院の正門
基本的に宿舎と病院の往復だけです。病院は宿舎から徒歩10分足らずの距離でしたが、安全上の理由で、ひとりでの外出は控えるように要請されていたので、車での移動でした。1ヵ月の滞在中に2回だけ、数人で病院から宿舎まで歩いて帰りました。それだけのことで、とても開放感を感じました。
イスラム教徒の方々が多く暮らしている地域なので、現地滞在中はアルコールを一切見ませんでした。ただ、個人的にはアルコール摂取を控えていたので、まったく苦痛ではありませんでした。
蚊帳、殺虫剤、虫除けは完備されていましたが、蚊を見かけることは多く、わずかとはいえ熱帯医学の知識があるので、マラリアの恐怖を常に感じていました。
宿舎では個室が用意されていました。一度だけ約1日半断水がありましたが、基本的に電気、水道そしてインターネットは常時使用可能でした。インターネットの接続速度は、動画サイトの視聴が厳しいレベルですが、テキストのメールなどは問題なくできました。
- Q活動中、印象に残っていることを教えてください。
-
 お別れパーティーでダンスに参加(筆者中央)。
お別れパーティーでダンスに参加(筆者中央)。
踊る日本人をみんなが楽しそうに見てくれた。ちょうど私以外にも2人の海外派遣スタッフが同時期に活動期間を終えることになり、病棟の患者さんたちと一緒の大きなお別れパーティーが企画されました。ビンゴ大会やダンスなど、大いに盛り上がりました。初めは恥ずかしくて辞退していたのですが、「土地の人びとの気持ちに応えよう」とのアドバイスを受け、ダンスの輪にも参加しました。
苦労したことは、スタッフに対しては医学的に適正な手順や物事の考え方などを常に説明するのですが、さまざまな理由から受け入れられないこともあることです。たとえば、清潔操作や薬剤の温度管理などにおいて、文化的な背景、物理的な制約、個人的な性格などいろいろな理由から、受け入れられないことがありました。
- Q今後の展望は?
-
小さな診療所での外来診療に戻ります。微力ながら地域医療の為に働きます。 機会があれば、短期間の活動に再び参加したいです。
もしかしたら、もう自分が実際に活動地へ行く事は難しいかもしれませんが、今の仕事を続けながらも、派遣されるスタッフを支援できる機会があれば、積極的に参加したいと思っています。
- Q今後海外派遣を希望する方々に一言アドバイス
-
自身の経験からですが、さまざまな状況や制約があり、一概に本人の希望だけで簡単に派遣が決まるような話では無いと思います。自分一人では解決できないような障害があることも考えられます。
ただ、MSFでの活動は間違いなく人びとの役に立つものであるし、自分が得るものも大きいです。人道援助という世界を知り、関心を持ち続けている人間に自分を変えるきっかけを与えてくれたのはMSFです。感謝しています。
MSF派遣履歴
- 派遣期間:2009年1月~2009年3月
- 派遣国:リベリア
- プログラム地域:モンロビア
- ポジション:小児科医
- 派遣期間:2008年8月~2008年12月
- 派遣国:スリランカ
- プログラム地域:キリノッチ
- ポジション:小児科医
- 派遣期間:2008年5月~2008年6月
- 派遣国:ナイジェリア
- プログラム地域:コンタゴラ
- ポジション:小児科医







