海外派遣スタッフ体験談
戦闘の混乱で医療を受けられない患者のために
伊藤 謙
- ポジション
- 内科医
- 派遣国
- 南スーダン
- 活動地域
- ワウ
- 派遣期間
- 2016年6月~2016年9月
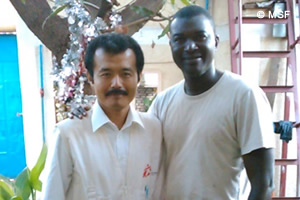
- Q国境なき医師団(MSF)の海外派遣に再び参加しようと思ったのはなぜですか?また、今回の派遣を考えたタイミングはいつですか?
-
これまでの派遣経験を通じて、医療サービスをなかなか受けることができない患者さんに、今まで培った臨床経験を用いて貢献したいという思いが強まったからです。
- Q派遣までの間、どのように過ごしましたか? どのような準備をしましたか?
-
前回のヨルダンでの活動中に病気となってしまい、今回の派遣までの間、手術を受け体調の回復をはかりました。MSFの治療指針を読みつつ、現地到着後直ちに治療にあたることができるよう準備しました。
英語に関しては、スカイプを用いた英会話、英単語の覚えなおし、日常生活のすべてを常に英語で表現すること、英語リスニング(スクリプトで本当のところ何と言っているのか確認しつつ)を実践し続けました。どれも大変に英語力向上に有効でした。日本製の箸を現地へのお土産とすべく購入しました。
- Q過去の派遣経験は、今回の活動にどのように活かせましたか? どのような経験が役に立ちましたか?
-
今回は3度目の派遣でした。英会話に関しては、過去2回を大きな問題なくこなすことができたので、今回も不安なく任務を遂行できました。
1回目の南スーダンの派遣内容が今回の任務と似ていたので、その時の経験を生かして治療にあたりました。2回目のヨルダンへの派遣時は、現地の医師への指導が主な仕事内容でしたが、この時養った良好な対人関係の構築方法や苦情処理の経験を今回の任務で生かせました。
- Q今回参加した海外派遣はどのようなプロジェクトですか?また、具体的にどのような業務をしていたのですか?
-
西ハバル・エル・ガザル州のワウ及びその近辺で、政府軍と反政府軍が戦闘を繰り返し、現地の人びとは森林の中で隠れ住んでいました。そんな状況で、小児の栄養失調が深刻になりました。ワウ市内にある病院も医療スタッフが安全確保のため逃げてしまい、十分機能しなくなりました。今回の活動は、医療を受けられないまま隠れ住んでいる人びとに医療サービスを提供することです。
緊急援助であり、また私の活動期間中に紛争が悪化したことにより、活動内容は時間とともに変化しましたが、基本的に医療チームが村々や、人びとが隠れている地域に自動車で赴いて医療サービスを提供する、いわゆる移動診療が主な活動内容でした。派遣スタッフは5人(医師は私のみ)、現地スタッフは現地のクリニカル・オフィサー(准医師)2人、運転手とガードマンが多数、プロジェクトのロジスティック面を担当するスタッフ3人と、多くの人数がプロジェクトにかかわっていました。主な症例は、マラリア、肺炎、栄養失調でした。
- Q派遣先ではどんな勤務スケジュールでしたか? また、勤務外の時間はどのように過ごしましたか?
-
 ワウの病院で看護師たちと
ワウの病院で看護師たちと
まず、休みの日がほぼありませんでした。自由時間は、医療活動中に得られたデータの解析・報告の作成に充てていました。仕事は、朝7時から夜7時まで続きました。いくら食べても体重が減ったので、それなりに精神的重圧がかかるプロジェクトだった印象です。
6月の終わりまでは、移動診療が主な仕事でした。朝7時に事務所を出発して活動先の村を目指します。村に着くと現地スタッフを数人雇い、列を作って待つ患者さんを診察し、処方薬を渡します。ワウ郊外に政府軍の検問所があり午後4時にワウへの通行路が閉鎖されます。したがって、午後2時30分頃には活動を終了して帰路につきます。
6月の終わり頃、ワウで戦闘が起きました。数日間、市内の国連施設に避難しました。この戦闘で多くの避難民が国連施設に隣接する難民キャンプに殺到したため、ここでも移動診療を立ち上げ、ほかのNGOと協力して行いました。
この時、銃創を負った6人の患者を飛行機で首都にある病院に搬送することになり、私が引き受けることとなりました。機内では定期的にバイタルサインを確認しつつ患者を慰め励ましていました。これまでにない経験でした。
この頃、プロジェクトの活動内容が変わりました。移動診療を終了し、ワウに近接する複数の村に簡易診療所を設立して現地の医療スタッフを雇用し、彼らに医療を行ってもらう形にしました。MSFは、診療所に定期的に医薬品を配給することとなりました。
同時にワウ市内に栄養失調・急性期重症小児患者を対象とした病院を設立・運営することとなりました。7月下旬に病院は完成し、私はそこでの診療とクリニカル・オフィサーの監督が仕事となりました。
7月初旬に、反政府軍が支配する村で政府軍との戦闘が起こり、簡易診療所への薬の定期的な補給が一時期不可能となりました。そのため、この頃の活動はワウの病院での業務が主になりました。勤務時間は朝7時30分から夜7時まででした。昼食は、地元のレストランで取りました。パンとヤギ肉を好んで食べました。たくさんのハエが飛んでいましたが、味はおいしかったです。
7月末に、この病院に派遣スタッフの小児科医師が合流しました。ちょうどこの時期、州都アウェイルにあるMSFの病院でマラリアまん延に伴う医師不足が深刻となり、私は8月中旬まで勤務地をワウからアウェイルに移しました。
アウェイルの病院は、すでにMSFによって数年間運営されており、その組織体系は確固たるものです。また、アウェイルは1つの部族により占められていたので部族間闘争がなく比較的安全でした。勤務時間は、朝8時ごろから午後6時頃まででした。昼食は、ゲストハウスに戻り食べました。メニューが豊富でした。
ここでは、病棟勤務、夜間オンコールが主な仕事でした。マラリア、1型糖尿病、外傷、結核、肺炎をはじめとする感染症が主な症例でした。複雑な神経内科疾患やネフローゼ症候群も見られ大変に勉強となりました。ただし、3週間の滞在中、上気道炎を継続して患い、仕事以外の時間は寝ていました。
8月中旬にワウに派遣されていた小児科医師が帰国となり、私が再びワウへ呼び戻され、病院勤務となりました。この頃、目立った紛争は起こらず、移動診療と村への薬の供給が再開されていました。移動診療と薬の供給は、1人のベテランのクリニカル・オフィサーが担当していました。現地のクリニカル・オフィサー、看護師、栄養士、掃除をするスタッフ、ガードマン、運転手とはよく言葉を交わし、充実した病院勤務の日々でした。
空き時間には、翌日の業務に向けてベッドで休んで体力の回復をはかりました。インターネットの接続環境が劣悪でした。パソコンに入れておいた洋画を見つつ精神的重圧の軽減に努めました。私はかつて武道を練習していたので、現地スタッフへの日本の紹介の一環として演武を見せました。みなさん興味津々でした。
- Q現地での住居環境についておしえてください。
-
着任当初は事務所に寝泊まりしていました。7月中旬にゲストハウスを借りたので、そちらでの生活となりました。コンクリートでできた、かつてホテルだった建物で、トイレとシャワーが各部屋についていました。ベッドには蚊帳が装備されていました。
ただ、蚊があまりに多く、いつの間にか蚊帳の中に潜入し刺してくるので、日によっては寝不足でした。
食事は、朝は現地スタッフが購入してきた出来立てのパンとコーヒーでした。昼食は、ご飯とヤギ肉でした。夕食も昼食とほぼ同様でしたが、おなか一杯食べることができました。しかし、忙しかったせいか、体重は減少しました。昼食と夕食は現地の女性が雇用され作ってくれました。
洗濯物はかごに入れておけば、料理をする女性が空いた時間に行ってくれていました。大変助かりました。
治安を考慮して、外出は派遣スタッフ2人以上でないと許可されませんでした。夜7時以降は車での外出しか許されていませんでした。安全管理をしっかり守っていたので、基本的に身体の危険に遭遇することはありませんでした。仕事が多忙で街の散策という欲求もわきませんでした。
市場での物価は、日々上昇していました。私だけでなく現地スタッフもそのことについて文句を言っていました。コーラの値段が日々上昇することで閉口しました。
- Q活動中、印象に残っていることを教えてください。
-
国籍、肌の色、言葉、生活環境の違いがあっても、一生懸命患者さんに尽くすと、患者さんのみならず現地スタッフもその熱意を理解してくれました。
マラリアは貧血を起こします。重症な貧血の際は輸血を必要とします。まだ、2歳の女児はドナーが見つからなくて命を落としました。7歳の女児が敗血症で治療の甲斐亡くなりました。新生児破傷風の赤ん坊も、急変して亡くなってしまいました。これらのことは、たいへん悔しく残念でした。
- Q今後の展望は?
-
MSFの活動を通じて、医療サービスを受けることができない患者さんに尽くすことができました。患者さんのための医者であろうと、医師になった時から日々心でつぶやき診療にあたって来ました。この心は海外での医療現場で通用しました。これからは、再び日本の患者さんに尽くしていこうと思います。
- Q今後海外派遣を希望する方々に一言アドバイス
-
挑戦してみたいなと少しでも心に抱いた方は、ぜひ諦めずに前進してください。私にできたのですから自信をもって挑戦してください。皆さんなら大丈夫ですよ。
MSF派遣履歴
- 派遣期間:2015年8月~2016年4月
- 派遣国:ヨルダン
- 活動地域:イルビド
- ポジション:内科医
- 派遣期間:2014年10月~2015年1月
- 派遣国:南スーダン
- 活動地域:パマト
- ポジション:内科医







