法務局での遺言書保管制度とは? 自筆証書遺言の無効にならない残し方を解説
更新日:2025年9月17日
監修者:庄田和樹(司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役)

法務局の自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局にある遺言書保管所で保管してもらう制度です。遺言書を安全に保管するほか、遺言者の死後に発生する手続きをスムーズにするなどのメリットがあります。今回は自筆証書遺言書保管制度の概要や注意点、利用の流れなどをわかりやすく紹介します。
目次
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
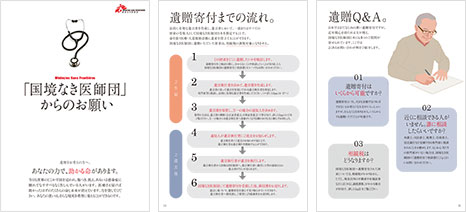
国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
- 国境なき医師団の活動内容
- 遺贈寄付で実現できること
- 遺贈寄付者の声

1.遺言書の種類
一般的に用いられることの多い遺言書に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きで作成する遺言書です。それに対し公正証書遺言は、重要文書の作成などの役割を担う「公証役場」という公的機関で作成する遺言書です。
なお、内容を秘密にしたまま遺言書の存在のみを証明する「秘密証書遺言」と呼ばれる遺言書もあります。しかし、知名度が低く、遺言の内容が書式の不備等により無効になるリスクもあることから、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて選択するメリットは少ないでしょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者(遺言を作成する人)が自ら作成する遺言書で、紙とペン・印鑑があれば思い立った時に作成できます。
- 特徴
- 作成のための費用がいらない
- 自分で書き直しができる
- 遺言書の内容を秘密にできる
一方、遺言書は重要な文書であるため、法律に記載された通りの方法で作成することが求められます。自筆証書遺言の場合は「遺言者が全文・日付・氏名を自書すること」「印を押すこと」(※1)などの決まりがあり、要件を満たすために慎重に作成する必要があります。
また、遺言者の死後、遺言書を発見した保管者や相続人は、家庭裁判所で「検認」と呼ばれる手続きを行う必要があります(※2)。これは相続人に遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書の偽造・変造を防止するために行うものです。
- 注意点
- 要件を満たしていなければ無効になる
- 紛失したり、発見されなかったりするリスクがある
- 改ざん、破棄されるリスクがある
- 家庭裁判所で検認の手続きが必要になる
しかしながら、法務局での自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、この「検認」の手続きを行う必要がなくなります。法務局での自筆証書遺言書保管制度のさまざまなメリットは後ほどご説明します。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人(公正証書の作成などを担当する法律の専門家)と証人2人以上の立ち会いの下で作成する遺言書です。
- 特徴
- 公証人の確認の上で作成するため、無効になる可能性が低い
- 改ざんや破棄のリスクがない
- 遺言者の死後、検認の手続きをする必要がない
公正証書遺言は法律の専門家である公証人が作成するため、法的な要件を満たしていないために遺言書が無効になる可能性は極めて低いと言えます。遺言書の作成後は、原本を公証役場で保管します。そのため、悪意のある誰かに勝手に書き換えられたり、破棄されたりする心配はありません。
しかし、公正証書遺言は信頼性が高い反面、作成手数料を公証役場に支払う必要が生じます。また、相続関係が複雑になる場合には、遺言書の作成段階で弁護士、司法書士、行政書士などの専門家に依頼することも多いため、別途その費用も用意することになります。
- 注意点
- 証人を2人以上手配する必要がある
- 作成費用がかかる
- 公証人との打ち合わせや準備を行う手間がかかる
2.法務局の自筆証書遺言書保管制度とは
「自筆証書遺言書保管制度」は、自筆証書遺言を全国の法務局で保管してもらうための制度です。
前述した通り、自筆証書遺言は任意の場所でいつでも作成できる反面、法的な要件を満たしていないために遺言が無効になるリスクがあります。さらに、遺言書を誰かに開封されてしまい、勝手に改ざん・破棄されてしまう可能性もないとは言えないでしょう。遺言書をどこにしまったか忘れてしまったり、死後に遺言書が発見されなかったりするケースもあります。
このような自筆証書遺言の課題に対応するため、2020年7月10日から始まったのが自筆証書遺言書保管制度です。遺言書の原本及び画像データが法務局に保管されるため、安心して遺言書を残せます。
次項から、自筆証書遺言書保管制度のメリットや注意点、利用する際の流れなどを見ていきましょう。
自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言の課題に対処しながら、よりリスクや手間の少ない形で遺言書を残せるメリットがあります。具体的なポイントは以下の通りです。
① 適切に保管されるため、書き換え・破棄・紛失・隠蔽を防げる
法務局で遺言書の原本と画像データを保管できるため、書き換えや破棄といった行為から遺言書を守れます。
② 法務局職員(遺言書保管官)が形式を確認するため無効になりにくい
保管申請を行う際は、法律で定める遺言書の形式に適しているかどうか、手続きを担当する法務局職員(遺言書保管官)にチェックしてもらえます。なお、チェックを受けられるのは「本人の手書きと押印」「正確な日付の記載」など、主に見た目から判断できる要件です。あくまで外形的なチェックであるため、本人以外が書いたりした場合、相続の内容が明確でない場合、また遺言者の遺言能力が疑われる場合などは、必ずしも遺言書が有効になるというわけではありません。
③ 相続人に発見してもらいやすい
遺言者の死後、一定の条件の下で、関係相続人等(法定相続人、遺言書に書かれた受遺者、遺言執行者など)に遺言書が保管されていることを通知してもらうことができます(関係遺言書保管通知)。遺言者があらかじめ指定した方(通知対象者)に対して、遺言書が保管されている旨を通知してもらうことも可能です(遺言者が指定した方への通知)。通知する方を指定する場合は、申請書類の専用の項目に最大3人まで記載できます。
④ 検認が不要
自筆証書遺言は本来、遺言者の死後、家族が遺言書を見つけても勝手に開封することはできません。偽造・変造を防止するために家庭裁判所に遺言書を提出し、検認を請求する必要があります。この検認を終えないと、預貯金の払い戻しを受けたり、不動産の名義変更をしたりするなど、遺言書に基づいて遺産を分割するための手続きが行えません。
しかし、自筆証書遺言書保管制度は法務局に遺言書の原本や画像データが保管されるため(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)、偽造・変造を防止できます。このことから、保管制度を利用した自筆証書遺言は検認の手続きが不要になります。
自筆証書遺言作成の注意点
自筆証書遺言が無効にならないように、民法で定められた要件をよく確認した上で作成することが大切です。前述の通り、法務局へ保管申請をする際に確認してもらえるのは、外形的な内容のみですので、よく注意して作成しましょう。主なポイントを紹介します。
- ① 自書と押印
- 遺言者が遺言書の全文を自書する
- 氏名を自書する(自筆証書遺言書保管制度を利用する際は、戸籍と同じ氏名にする)
- 日付を具体的に年月日で自書する(「令和7年7月吉日」等は不可)
- 押印する
- ② 財産目録を添付する場合
- 財産目録を別紙で添付する場合は自書する必要はなく、パソコンで作成することができる
- 財預金通帳、登記事項証明書等のコピーでも財産目録として認められる
- 別紙を添付する場合は、ページごとに手書きの署名と押印が必要
- ③ 修正や追加をする場合
- 遺言書の内容を変更する場合は、二重線を引き、押印をする
- 変更した部分がわかるように具体的に示した上で署名を行う(「3行目、3字削除2字追加 田中太郎」など)
- 修正テープや修正液は使用しない
遺言書の内容や有効性に不安が残るときは、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に内容確認を依頼してもよいでしょう。
自筆証書遺言書保管制度を利用する際の注意点
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、民法上の遺言書の要件はもちろん、制度を利用するための要件も満たす必要があります。主なポイントは以下の通りです。
- 紙はA4サイズで、文字が読みにくくなるような模様等がないもの
- 上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートルの余白を確保する
- 各ページの余白内にページ番号を記載する(1/3、2/3、3/3など)
- 紙が複数枚あってもホチキス等で綴じない
- 消えるインク等ではなく、ボールペンや万年筆といった消えにくい筆記用具を使用して書く
自筆証書遺言書保管制度の利用の流れ
自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、遺言書を作成した上で、遺言者本人が法務局の遺言書保管所で手続きを行います。具体的な流れは以下の通りです。
① 遺言書を作成する
本ページなどで紹介した要件を確認しながら、遺言書を作成します。封筒やホチキス留めは不要です。
② 法務局を選ぶ
以下のいずれかの遺言書保管所を選択します。
- 遺言者の住所を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
遺言書保管所の場所や連絡先は以下のページから確認できます。
③ 遺言書の保管申請書を作成
手続きに必要な申請書は、法務局のホームページのほか、窓口で入手することも可能です。
申請書には、遺言者本人の情報に加え、受遺者(財産を譲り受けることになる方)や遺言執行者(遺言内容を実行するための手続きを行う方)等の情報も記載します。また、遺言者の死亡時に通知してほしい方(通知対象者)がいれば、該当する項目も記載します。
④ 予約
「法務局手続案内予約サービス」のページから手続きの予約を行います。また、電話や窓口でも予約を受け付けています。
⑤ 申請
予約した日時になったら、以下の必要書類を持って遺言書保管所へ行き、手続きを行います。
- 遺言書
- 申請書
- 添付書類(住民票の写し等)
- 官公署から発行された顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 1通につき3900円分の収入印紙
書類が無事に受理されると「保管証」が受け取れます。保管証は再発行できないため、大切に保管しましょう。
3.自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合の相続人の対応
遺言者が自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、遺言者の死後に相続人が遺言の内容を閲覧できます。遺言書は画像データとして保管されているため、全国の法務局に対して遺言書の閲覧の請求が可能です。閲覧の際は、事前に法務局手続案内予約サービスもしくは電話・窓口での予約を行います。
また、不動産の相続登記や銀行口座の解約手続きに必要な遺言書情報証明書もあわせて発行できます。手続きのためには「遺言書の閲覧の請求書」「遺言書情報証明書の交付請求書」などの書類の準備が必要です。
4.まとめ
自筆証書遺言は遺言者が思い立ったタイミングで手軽に作成しやすい遺言書です。その反面、法的な要件を満たしていないために遺言内容が無効になったり、改ざんや紛失・隠蔽の可能性があったりするなどの懸念もあります。
これらをはじめとするリスクを軽減するために始まったのが、法務局の自筆証書遺言書保管制度です。遺言書を法務局で安全に保管することはもちろん、遺言者の死後に家庭裁判所での検認が不要になることや、相続人等に対して通知が行われるなどのメリットがあります。法務局の遺言書保管所は全国に300カ所以上あり、自筆証書遺言書保管制度が始まった2020年7月10日から毎年約2万件の保管申請がされています。自筆証書遺言を選択される方は、保管制度を利用することを検討されてみてはいかがでしょうか。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
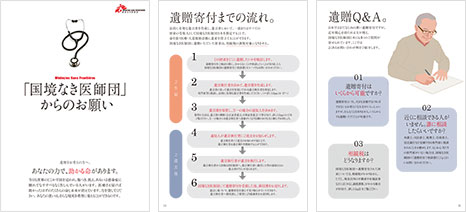
5.遺贈寄付に関するご相談
遺贈寄付の手続きは、誰にとっても初めての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聴かれます。「国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口
遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。
国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
-
電話03-5286-6430
- ※平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休
-
E-Maillegacy@tokyo.msf.org




















庄田和樹 司法書士・土地家屋調査士・行政書士 司法書士法人 土地家屋調査士法人 行政書士法人 神楽坂法務合同事務所 代表 ウィルサポート株式会社 代表取締役
信託銀行、司法書士法人勤務を経て独立。司法書士、土地家屋調査士、行政書士として相続等の問題の解決に注力するとともに、株式会社 遺言執行社を設立し、遺言書作成サポート、死後事務委任契約をはじめとする専門的なサービスを提供している。