遺言書を保管する─遺言書の保管方法と注意点─

遺贈が実現するためには、法的に有効な遺言書を作成するだけでなく、作成した遺言書がご逝去後に発見され、破棄されたり改ざんされたりすることなく遺言執行者に届く必要があります。そのため、遺言書をどのように保管するかは重要なポイントです。
遺言書の保管方法は、公正証書遺言か、自筆証書遺言かによって利用できる制度が異なります。それぞれの特徴と方法の概要をまとめました。より詳しくは、専門家または遺贈寄付ご相談窓口までお問合せください。

遺言書の種類別にみる保管方法
公正証書遺言の場合は、遺言書を作成した公証役場が原本を、遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。そのため、原本の紛失や改ざんの心配はありません。ただし、ご逝去の連絡を、誰かが、公証役場と遺言執行者に行う必要があります。
自筆証書遺言の場合、これまでは、発見が遅れたり、発見されても遺言執行者の手に渡らなかったりするリスクがありました。しかし、新しく創設された法務局の遺言書保管制度を利用することにより、そのようなリスクを回避することができます。
詳しくは、法務省ホームページまたは「遺贈寄付ご相談窓口」にお問合せください。
これも知っておきたい─民法(相続法)の改正と遺言書保管法の制定─
自筆証書遺言の方式緩和
いままで、自筆証言遺言では、遺言書に添付する財産目録も自筆でなければなりませんでしたが、今回の民法改正によって、自筆証言遺言であっても財産目録についてはパソコンで作成することが可能になりました(※財産目録の各頁に署名押印をする必要はあります)。

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができるようになりました※1。
遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうか調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。※2 ※3
また、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には,あらかじめ遺言者が指定した者に対して,遺言書が保管されている旨を通知する「死亡時の通知」制度を利用すれば、遺言書の存在を確実に知ってもらえるので安心です。
- ※1作成したご本人が遺言書保管所に来て手続きを行う必要があります。
- ※2保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
- ※3遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人に対し、遺言書を保管している旨を通知します。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
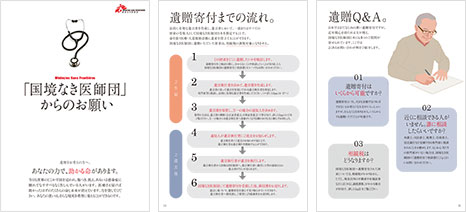
お問い合わせ
国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口
遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。
国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
-
電話03-5286-6430
- ※平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休
-
E-Maillegacy@tokyo.msf.org
- ©Julie Remy







