遺贈にかかる税金とは? 相続税の計算方法や注意点をわかりやすく解説
更新日:2024年10月9日
監修者:脇坂誠也 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク理事長(脇坂税務会計事務所 所長)
相続や遺贈の際にはさまざまな税金が発生します。そして、課税される税金の種類や税率は、誰が何をどれくらい受け継ぐのかによって、また、相続として受け継ぐのか、遺贈として受け継ぐのかによっても違います。ご自身の希望がちゃんとかなえられるように、また、遺贈が実現する際に、相続人と受遺者(じゅいしゃ)の間などで思わぬトラブルが起きることのないように、ご留意いただきたいことをご説明します。
- ※この記事では、NPO法人などが寄付として受け取る遺贈(遺贈寄付)だけでなく、遺言によって相続人以外の人が財産を受け取る遺贈も含めてご説明しています。
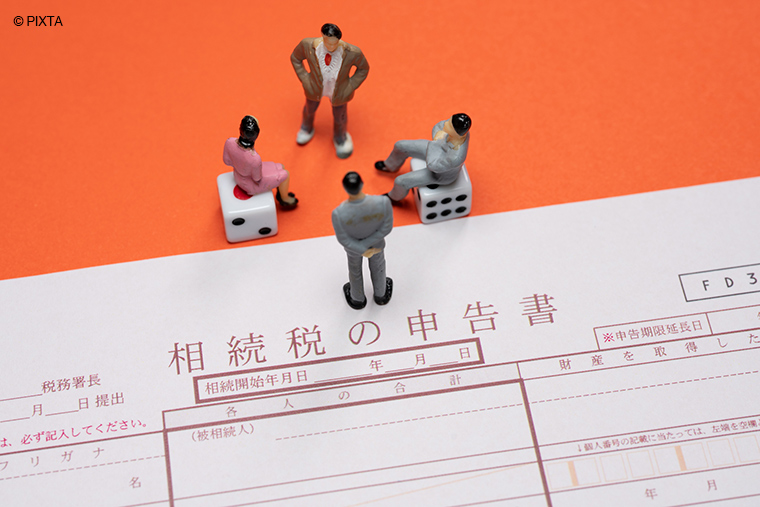
目次
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
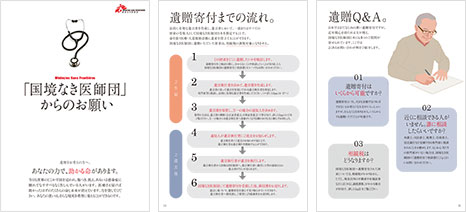
国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
1.遺贈とは?
遺贈とは、「遺言」により財産の一部または全部を無償で譲ることをいいます。遺贈をする人を「遺贈者(いぞうしゃ)」、遺贈を受ける人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。遺贈者と被相続人は同一です。
相続により財産を譲り受けることができるのは民法で定められた法定相続人だけですが、生前に遺贈をする旨の遺言書を作成しておけば、法定相続人以外の人や団体、法人などにも財産を譲ることができます。「生前にお世話になった人がいる」、「死後に自身の財産を役立ててほしい慈善団体がある」などといった場合に、遺贈はご自身の希望をかなえる有効な手段となります。
遺贈は誰にできる?
遺言書があれば、法定相続分や遺産分割協議に優先して、遺言者の希望どおりに財産を譲ることができます。したがって法定相続人以外に財産を譲りたい対象がいる場合には、遺言書の作成が必須となります。ただし、配偶者、子(代襲相続人も含む)、直系尊属(被相続人の父母、祖父母)には、遺言によっても奪うことのできない遺留分が一定割合認められています。受遺者には誰を指定しても構いません。人以外に法人や団体へ遺贈することも可能です。財産を社会貢献活動に役立てるために、遺言で民間非営利団体や国、地方公共団体へ寄付することを遺贈寄付といいます。
- 受遺者が人の場合、次のようなケースが考えられます。
- 法定相続人以外の親族
老後の面倒をみてくれた息子の妻、内縁の配偶者、孫など - 生前にお世話になった友人、知人
- 一方、受遺者が法人や団体の場合、次のようなケースが考えられます。
- 母校など教育機関
高校、大学など - 非営利団体
NPO法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、社会福祉法人など - 医療機関
- 国
- 地方自治体
自分が生まれ育った、長い間そこで暮らしたなど、思い入れのある都道府県や市区町村
ただし、法人や団体への遺贈の場合、財産の種類や遺贈の形式などによっては受け入れていない場合もあります。遺贈を考えている団体等があるなら、生前に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。
ペットに財産を残したいという人もいるでしょう。ペットに財産を直接遺贈することはできませんが、信頼できる友人や知人などにペットの世話をしてもらえるよう飼育費を遺贈することは可能です。
なお、遺言書により法定相続人にも遺贈をすることはできますが、実務上は、相続人に財産を譲るときには遺言書に「相続させる」と記載するのが一般的です。
遺贈には税金がかかる?
遺贈に関連する税金として代表的なものは、相続税、みなし譲渡所得税、および不動産の遺贈に関連する税です。
相続税
遺贈により取得した財産は基本的に相続税の対象になり、受遺者が負担することになります。ただし、受遺者が(個人ではなく)法人の場合、相続税の負担が不当に減少する結果になるとされない限り、相続税は課税されません。
こうした法人への遺贈は、遺贈をした分だけ相続財産を減らすことができるため、相続税の節税につながります。また、寄付先が国や地方公共団体、特定の公益法人、認定NPO法人などの場合には、被相続人の生前の所得税を納税するために相続人が行う「準確定申告」の際、遺贈した金額を寄付金控除の対象にすることができ、所得税の節税にもつながります。
相続税は亡くなった方から財産を受け継いだ個人が納める税金であり、原則として法人に相続税は発生しません。しかしながら、有限会社や株式会社などへの遺贈の場合は法人税が課税される可能性があります。一方で、公益法人やNPO法人への遺贈の場合には、これらの法人は収益事業にのみ法人税が課税されるため、遺贈には法人税は課税されません。
みなし譲渡所得税
法人に不動産や有価証券など、現金以外の財産を遺贈する場合、その不動産や有価証券の時価が、取得費よりも高くなっていることがあります。
この差額分に対して課税されるのが、「みなし譲渡所得税」です。現行法では、不動産や有価証券などの財産が寄付先に移転しても、特定遺贈の場合には、納税義務だけは相続人に受け継がれることになるので、トラブルが起きやすいものです。不動産や有価証券を遺贈寄付する場合は、「みなし譲渡所得税」を誰に負担させるか、あるいはどこから差し引くのかを遺言書に明確に記載しておくことをおすすめします。
不動産の遺贈に関連する税
不動産を遺贈する際に、課税されることがあります。一つは上で説明した「みなし譲渡所得税」で、法人に不動産等を遺贈した場合で、不動産等の取得費よりも不動産を遺贈する時の時価が上回った際にかかる税です。もう一つは不動産取得税で、特定遺贈の場合にのみかかります。不動産の遺贈に関してどのような場合でも必要なのは、所有者の変更を登録する際の不動産登録免許税です。以下で詳しくご説明します。
図表1 不動産の遺贈に関連する税
| 税の名称 | 発生条件 | 負担者 | 負担額 | 申告期限 |
|---|---|---|---|---|
| 相続税 | 相続される財産の総額が基礎控除額を超える場合 | 財産を受け取った人(相続人・受遺者) | 相続額に応じて10%~55% | 相続開始を知った翌日から10カ月以内 |
| みなし譲渡所得税 | 法人に財産の贈与又は遺贈があった場合に、その贈与等される財産の時価が取得費を上回る場合 | 特定遺贈の場合には相続人、包括遺贈の場合には受遺者 | 取得費と現在の価格の差額に応じて | 相続開始を知った翌日から4カ月以内 |
| 不動産取得税 | 不動産の遺贈が相続人以外の人に対して特定遺贈として行われる場合 | 不動産の遺贈を受けた人 | 相続人以外の人が特定遺贈として受け取った不動産の価格の4%(令和6年3月31日までは3%) | |
| 登録免許税 | 相続・遺贈によって不動産の所有者が変更となる場合 | 不動産を受け取った人 | 相続人が相続または遺贈により取得した不動産については、0.4%。 他方、 相続人以外の者が遺贈により取得した不動産については、2% |
遺贈と相続の違いとは
遺贈と相続の違いは、大きく分けると次の3つです。
-
①
遺贈は財産を譲る対象が幅広く、相続は法定相続人のみ
-
②
遺贈は遺言書が必須、相続は遺言書がなくても可能
-
③
遺贈の方が相続よりも不動産の引き継ぎに手間がかかり、関連する税金も高い
順に見ていきましょう。
① 遺贈は財産を譲る対象が幅広く、相続は法定相続人のみ
相続により財産を譲ることができるのは法定相続人のみですが、遺贈は遺贈者が希望すれば法人等も含めて誰にでも財産を譲ることができます。
② 遺贈は遺言書が必須、相続は遺言書がなくても可能
ただし、遺贈を行うには生前に遺言書を作成しておかなければなりません。遺言書がない場合、財産を引き継げるのは法定相続人のみとなり、法定相続分で分けるか、遺産分割協議によって分けることになります。
③ 遺贈の方が相続よりも不動産の引き継ぎに手間がかかり、関連する税金も高い
不動産(土地・建物)を取得した場合、相続なら不動産を取得した相続人が1人で所有移転登記の申請をすることができます。所有権移転登記とは、該当する不動産の名義を変更するための手続きのことです。一方、遺贈の場合は、不動産を取得した受遺者(登記権利者)と遺言執行者または相続人全員(登記義務者)が共同で所有権移転登記の申請をしなければなりません。遺言執行者が遺言書で指定されていない場合は、相続人全員の協力が必要となります。遺贈で不動産を取得すると、相続で取得した場合よりも手間がかかるということです。
また、遺贈で不動産を取得した場合、相続で取得するよりも関連する税金の種類が増え、税率が高くなります。遺贈による不動産の取得にかかる税金として相続税のほか、不動産取得税(不動産を取得した場合にかかる地方税)と登録免許税(登記の手続きの際にかかる国税)がかかる場合があります。
一方、相続の場合、不動産取得税はかからず、相続税のほかには登録免許税しかかかりません。しかも登録免許税の税率は遺贈の場合よりも低くなります。
遺贈の場合、特定の財産を指定して譲る「特定遺贈」により不動産を引き継ぐと、受遺者には相続税に加えて不動産取得税と登録免許税の両方がかかります。
財産の内容を特定せずに、「財産の全部」あるいは「財産の何割」などといったように譲る「包括遺贈」という方法で不動産を引き継いだときは、受遺者に不動産取得税はかかりませんが、登録免許税は特定遺贈の場合と同じ率でかかります。
遺贈を受けた際に発生する税金は「相続税」に当たる
法定相続人も遺贈の対象になりますが、実務上では、遺贈とは相続人以外の人が遺言書により相続財産を取得することをいいます。相続財産の取得ということから、財産を譲り受けた受遺者にかかる税金は相続税となります。遺贈には「贈」の漢字が入っているので贈与税と勘違いしそうですが、相続税なので注意しましょう。
遺贈に似た財産の譲り方に、「死因贈与」があります。死因贈与も遺贈と同様に、法定相続人以外の人に死後に財産を譲ることができる方法です。
遺贈は、遺贈者が遺言書により一方的に受遺者に財産を譲ることを伝える「単独行為」です。ですから受遺者は遺贈者が亡くなるまで、遺贈者が自分に財産を残してくれていたことに気が付かない場合が多いでしょう。
一方、死因贈与は死後に財産を譲ることを、生前に贈与をする人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)との間で契約をする「契約行為」なので、受贈者は贈与者の死後、財産が残されることを知っています。死因贈与の場合も受贈者にかかる税金は贈与税ではなく相続税となります。贈与税がかかるのは、贈与者が受贈者に「生前贈与」(存命中に行う贈与)をした場合のみです。
2.遺贈を受けた場合の相続税の計算方法・計算式
遺贈を受けた場合、相続財産の金額によっては相続税がかかってきます。相続税がいくらになりそうなのか、計算方法を知って試算しておくと、納税額の心積もりができます。図1の3つのステップに沿って、例も交えながら紹介しましょう。ただし、ここで紹介する金額は概算なので、実際にいくらかかるのか正確な金額を知りたい方は、税理士などの専門家に依頼するとよいでしょう。
図1 遺贈を受けた場合の相続税の計算手順
-
【Step1】
相続財産を全て洗い出し、課税遺産総額を計算する
-
【Step2】
課税遺産総額を基に相続税の総額を計算する
- ① 各法定相続人の遺産の取得金額を出す
- ② 各法定相続人の取得金額に所定の相続税率を掛け、各人の相続税額を計算する
- ③ ②で計算した金額を合計し、相続税の総額を出す
-
【Step3】
受遺者も含め各人が実際に納める相続税を計算する
【Step1】相続財産を全て洗い出し、課税遺産総額を計算する
はじめに、相続財産を全て洗い出し、正味の遺産額を計算します。
相続税の課税対象となるものには以下のようなものがあります。
- (A)
- 預貯金、債券、株式などの金融資産、不動産など、被相続人の所有財産
- 生命保険金や死亡退職金といった「みなし相続財産」
- 暦年贈与における相続開始前3年以内の贈与財産
- 相続時精算課税贈与におけるすべての贈与財産
生命保険金や死亡退職金は、相続財産ではありませんが、相続税の申告上は相続財産とみなして計算されます。
また、故人の生前に「暦年贈与」が行われていた場合は相続開始前3年以内の贈与財産を、「相続時精算課税贈与」が行われていた場合はすべての贈与を、相続財産の課税対象金額に含める必要があります。
それぞれの財産がいくらになるか、相続税の計算ルールに基づいて計算し合計額を出します。そこから差し引ける金額もあります。差し引ける金額には、(B)と(C)があります。
- (B)
- 非課税の財産(墓地、墓石、生命保険金の非課税枠など)
- 葬式費用
- 被相続人の債務(借入金など)
- 法人へ寄付をした金額(ただし、相続税の負担を不当に減少する結果となると認められる場合は除く)
- (C)
- 基礎控除額
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
(A)の課税対象となる財産から(B)を差し引いたものが「正味の遺産額」です。
計算式は
(A)の総額−(B)の総額=正味の遺産額
となります。
正味の遺産額から、(C)基礎控除額を差し引くと、「課税遺産総額」になります。つまり、
(A)の総額―(B)の総額―(C)=課税遺産総額
となります。なお、課税遺産総額が0円以下になった場合には相続税はかかりません。
【Step2】課税遺産総額を基に相続税の総額を計算する
次に、【Step1】で計算した課税遺産総額を基に相続税の総額を計算します。
ここからは説明だけでは分かりにくいので、例を挙げながら話を進めていきます。
- 例)
- 正味の遺産額 1億800万円
- 法定相続人 配偶者(妻)、子2人(長男、長女)
- 基礎控除額 3000万円+600万円×3人(法定相続人の数)
- 課税遺産総額 6000万円
- 法定相続人以外の受遺者 被相続人の知人1人
① 各法定相続人の仮の遺産の取得金額を出す
相続税の総額を計算するには、まず課税遺産総額を法定相続人に応じた法定相続分で分けたと仮定して、各人の遺産の取得金額を出します。この取得金額は、相続税を計算するうえでの便宜上の金額なので、相続財産を受け取る人の中に受遺者がいる場合を含め、実際に各法定相続人が受け取る遺産の金額とは異なる場合があります。
ここに挙げた例では、法定相続人は妻と子2人(長男、長女)です。この場合の妻の法定相続分は2分の1、長男、長女の法定相続分は1人につき4分の1なので、各人の遺産の取得金額は
- 妻 6000万円×1/2=3000万円
- 長男 6000万円×1/4=1500万円
- 長女 6000万円×1/4=1500万円
となります。
② 各法定相続人の取得金額に所定の相続税率を掛け、各人の相続税額を計算する
次に、①で計算した各法定相続人の取得金額に所定の相続税率を掛け、控除額を差し引いて、各人の相続税額を計算します。相続税の計算をする際には、「相続税の速算表」(図表4)に当てはめて計算します。 すると
- 妻 3000万円×15%−50万円=400万円
- 長男 1500万円×15%−50万円=175万円
- 長女 1500万円×15%−50万円=175万円
となります。
図表4 相続税の速算表
| 法定相続分に応じた取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7200万円 |
③ ②で計算した金額を合計し、相続税の総額を出す
②の相続税額を合計し、相続税の総額を出します。
すると
- 相続税の総額=400万円+175万円+175万円=750万円
となります。
【Step3】受遺者も含め各人が実際に納める相続税を計算する
【Step2】までで相続税の総額が出ました。各人が納める相続税を計算するには、正味の遺産額(ここでは1億800万円)に対して各人が実際に取得した遺産の割合(実際に取得した遺産の金額/1億800万円)で750万円の相続税額を按分します。
妻が7200万円、長男が900万円、長女が900万円、受遺者である被相続人の知人が1800万円の遺産を取得したとすると、それぞれが納める相続税額は
- 妻 750万円×(7200万円/1億800万円)=750万円×2/3=500万円
- 長男 750万円×(900万円/1億800万円)=750万円×1/12=62万5000円
- 長女 750万円×(900万円/1億800万円)=750万円×1/12=62万5000円
- 被相続人の知人 750万円×(1000万円/1億800万円)=750万円×1/6=125万円
となります。ただし、受遺者である被相続人の知人の相続税は2割加算となります。
そのため、実際に被相続人の知人が納める相続税額は
125万円×1.2=150万円
となります。
なお、実際には妻は相続税の配偶者控除が受けられるため、取得した遺産の全額が1億6000万円あるいは法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。上記の例では、計算上の妻の相続税は500万円ですが、納める必要はありません。ただし、配偶者控除を受けた旨の相続税の申告は必要です。
3.遺贈に関する注意点
遺贈は法定相続人以外に財産を残せるので、ご自身が亡くなった後の財産の引き継ぎ先の選択肢を増やせるというメリットがあります。ただし、利用する際にはいくつか気を付けなければいけないこともあります。主な注意点をまとめました。
相続税の基礎控除の計算には遺贈を受ける人を含めない
遺贈は、一定の要件を満たした団体等への遺贈寄付を除くと、基本的に相続税の対象となります。相続税を計算する際、相続財産の総額を出し、そこから差し引ける金額を差し引いて課税対象となる遺産総額(課税遺産総額)を計算します。
相続税から無条件で差し引けるのが「基礎控除」といわれるものです。
基礎控除は
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
という計算式で求められます。
法定相続人が3人なら、基礎控除額は
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
となります。法定相続人の数が増えるほど基礎控除額も増え、それだけ課税遺産総額を減らすことができ、相続税の負担が軽減されます。ただし、法定相続人以外の人数は基礎控除額の計算には含まれません。遺贈により遺産を取得した受遺者が何人いても、それが法定相続人以外の人であれば基礎控除の計算式には含まれず、課税遺産総額を減らす効果はないということを心に留めておきましょう。
ただし、前述の一定の要件を満たした団体等への遺贈寄付の場合、寄付した遺産の額を相続財産から差し引くことができるので、相続税の節税効果が期待できます。
遺贈を受けると相続税は2割加算になることがある
被相続人の一親等の血族(子、父母、および被相続人と養子縁組した人。代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の人が遺贈を受けて相続税が課される際、税額は各人の算出相続税額に2割の加算となります。
ただし、被相続人の養子となっている被相続人の孫は、被相続続人の子が相続開始前に死亡したときや相続権を失ったためその孫が代襲して相続人となっているときを除き、相続税額の2割加算の対象になります。
相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額 = 各人の税額控除前の相続税額×0.2(国税庁HP)
法定相続人以外は、死亡退職金・死亡保険金に非課税枠がない
相続財産となる死亡退職金や死亡保険金にはそれぞれ下記の非課税枠があります。非課税枠の分だけ相続税の課税対象になる金額を減らすことができます。
- 死亡退職金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
- 死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
例えば、死亡保険金が3000万円で法定相続人の数が4人なら
非課税枠=500万円×4人=2000万円
となり、相続税課税対象額は
死亡保険金3000万円−非課税枠2000万円=1000万円
に減ります。ただし、死亡退職金にしても死亡保険金にしても、非課税枠が利用できるのは法定相続人が死亡退職金や死亡保険金を受け取った場合です。遺贈により法定相続人以外が受け取った場合には、非課税枠を利用することはできないので、死亡退職金や死亡保険金は全額が相続税の課税対象としてカウントされます。誰を受取人に指定するかによって将来の相続税額が変わってくるので、注意が必要です。
不動産取得税・登録免許税などがかかる可能性がある
「遺贈と相続の違いとは」の項目で触れたとおり、不動産を遺贈により取得した場合には、相続税に加えて不動産取得税や登録免許税がかかる可能性があります。
「●●の土地をAさんに遺贈する」といったように、特定の財産を指定して遺贈された「特定遺贈」の場合、受遺者には不動産取得税と登録免許税の両方がかかります。
一方、「財産の4分の1をAさんに遺贈する」といったように、財産を一定の割合で遺贈された「包括遺贈」の場合に不動産が含まれていると、受遺者に不動産取得税はかかりませんが登録免許税はかかります。
登録免許税の税率は、特定遺贈でも包括遺贈でも「固定資産税評価額×2%」となります。これは相続により不動産を取得した場合の「固定資産税評価額×0.4%」よりも重い税負担となります。
親族以外は、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられない
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人の居住用または事業用だった土地を相続する場合に、一定の面積までの土地の課税評価額を80%または50%減額できるという特例で、利用できれば大きな節税効果が得られます。
小規模宅地等の特例は遺贈でも相続でも受けられることになっています。ただし、対象になるのは一定の要件を満たした親族です。親族とは配偶者、六親等内の血族、三親等内の姻族のことですが、特例の対象になるのは配偶者や同居の親族など非常に限定的です。したがって親族以外が遺贈を受けた場合には、小規模宅地等の特例の適用は受けられません。
なお、非営利団体等に寄付をする場合に、遺言で、被相続人が指定するのではなく、相続人が相続で取得した財産を寄付した場合には、以下の要件を満たしている場合には、相続税が非課税になります。
-
①
寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。 -
②
その取得した財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること。
-
③
寄付した先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の公益法人(独立行政法人や、社会福祉法人、一定の学校法人、公益社団・財団法人、認定NPO法人など)であること。
国境なき医師団は認定NPO法人ですので、相続人が相続により取得した財産を寄付した場合にも、上記の要件を満たせば、寄付をした財産は相続税が非課税になります。
4.まとめ
相続との違いも含めて、遺贈とはどのようなものなのか、遺贈の際の相続税の計算はどうするのか、注意点は何なのかなど、遺贈と税金に関する基礎知識をご紹介してきました。遺贈は生前築いてきた大切な財産を、死後に希望する人や団体等に譲る手段です。しかしご自身の希望を優先するあまり、将来、相続人に不満が生じてしまうのも残念なことです。また、受遺者にも過度な相続税の負担が生じないように配慮する必要もあります。遺贈を検討するなら、専門家ともよく相談し、遺言書を作成することをおすすめします。遺言書に遺贈を考えるに至った経緯などを「付言事項(遺言書にメッセージとして付け加えること)」として記載すると、相続人に気持ちが伝わりやすくなるでしょう。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
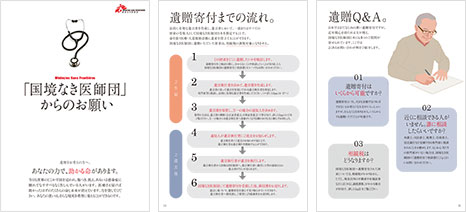
5.遺贈寄付に関するご相談
遺贈寄付の手続きは、誰にとってもはじめての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聞かれます。「国境なき医師団遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口
遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。
国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
-
電話03-5286-6430
- ※平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休
-
E-Maillegacy@tokyo.msf.org



















脇坂誠也 認定NPO法人NPO会計税務専門家ネットワーク 理事長 脇坂税務会計事務所 所長
理事長 脇坂税務会計事務所 所長
会計税務を通してNPOの健全な発展に寄与することを目指し、NPOの会計税務及びその周辺の情報、知識、ノウハウの発信にも力を入れている。