遺産分割とは? 手続き方法、手順、必要書類、費用の目安を紹介
更新日:2024年10月16日
監修者:三浦美樹 司法書士(日本承継寄付協会 代表理事)

遺産は遺言書の内容に従って相続しますが、遺言書がない場合には相続人同士で協議を行って分割方法を決めることになります。また、遺産の分け方には現物分割・換価分割といった方法があり、遺産の種類などによって適した方法を選択します。今回は、遺産分割の際の手続き方法などについて紹介します。
目次
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
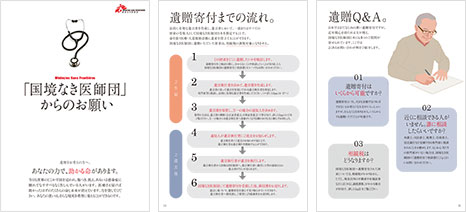
国境なき医師団の遺贈寄付の詳細
1.遺産分割とは何か
遺産分割とは、被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を相続人全員で話し合って決めることで、基本的に遺言書が遺されていない場合に行われます。この遺産分割には、民法で定められた被相続人の財産を相続できる人(法定相続人)全ての参加が必須となります。
被相続人が遺言書を遺さずに亡くなった場合、いったん相続人全員で遺産を共有している状態になります。誰がどのくらいの割合を相続するのかについては、法定相続割合(民法で定められた遺産相続割合)が一定の目安になりますが、具体的に誰がどの財産を相続するのかについては、遺産分割協議で決める必要があります。 遺産分割協議では、「現金がほしい」「建物がほしい」といった希望を伝えます。他の相続人が納得すれば、その希望通りに遺産を取得することになります。 また遺言書がある場合でも一定の割合を受遺する包括受遺者(割合的包括受遺者)がいる場合は、割合的包括受遺者も遺産分割協議に加わることができます。
2.遺産分割の手続きの種類と流れ
遺産分割は、まず「遺産分割協議」を行い、話がまとまらなかった場合は「遺産分割調停」「遺産分割審判」の順に進みます。
①遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員で遺産分割について協議を行うことです。誰がどの遺産をどんな割合で相続するのかを決定します。
相続人本人が出席することはもちろん、外部の専門家に依頼したり、高齢の親に代わって子どもが出席したりすることも可能です。特に、協議が長引きそうな場合や、相続人同士のトラブルに発展しそうな場合などには、弁護士などの専門家に依頼するケースもあります。 また、上述のように割合的包括受遺者も出席できます。
②遺産分割調停
遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
遺産の分け方を話し合う上では、相続人が感情的になって話が進まないこともあります。遺産分割調停とは、「調停委員」と呼ばれる立会人が公正・中立な立場で参加することで、妥当な解決を目指すものです。調停委員は相続人の言い分を聞きながら調停を進行し、解決策を探ります。
調停委員や裁判所と平日に予定を合わせなければならないので、調停期日(実際に調停が行われる日)を決めにくい点に注意が必要です。
③遺産分割審判
遺産分割調停でも話がまとまらなかった場合に行うのが、遺産分割審判です。調停が不成立となった際に自動的に移行するもので、改めて家庭裁判所への申し立てを行う必要はありません。
遺産分割審判では、当事者の主張や資料に基づいて遺産の分け方を決定します。調停は調停委員が間に入って行う話し合いであるのに対して、審判は遺産の分割方法を裁判官が決めるという違いがあります。
調停を行わず、初めから審判の申し立てを行うこともできますが、申し立ての際に「まずは調停によって話し合いを行ってみては」と促される可能性があります。また、遺産分割協議・遺産分割調停・遺産分割審判の一連の流れをまとめて弁護士に依頼するケースもあります。
3.遺産分割の4つの分割方法
ここでは、遺言書がない場合の遺産分割について説明します。
遺言書がない場合の遺産分割には、以下の4つの方法があります。
それぞれの分割方法について詳しく解説します。
①現物分割(げんぶつぶんかつ)とは
現物分割とは、「この土地は長男に、この車は次男に相続する」など、遺産を現物としてそのまま分ける方法です。
相続する遺産によっては金銭的な価値に違いがあるため、差が大きい場合には遺産の一部を売り払ってその代金で調整することもあります。また、価値の高い遺産を受け取った相続人が自分の資金で調整する「代償分割」を行うことで、不公平感を解消することも可能です。
②換価分割(かんかぶんかつ)とは
換価分割とは、遺産を売却して現金に換えてから分割する方法です。遺産をきっちりと公平に分割したい時に採用されます。
しかし、対象となる家や土地に相続人が住んでいる場合には、新しい家を探さなくてはなりません。また、不動産売却時の仲介手数料や、売却益が生じた際の譲渡所得税の申告・納税が生じることを覚えておく必要があります。
③代償分割(だいしょうぶんかつ)とは
代償分割とは、相続人が現物で遺産を取得し、それ以外の相続人に対して代償金を支払う分割方法です。
例えば、2000万円の不動産を相続する場合であれば、長男が不動産を取得し、長男が次男に対して1000万円の代償金を支払います。代償金の金額は、遺産の分け方として民法で定められている「法定相続分」を目安にして計算を行います。ただし、「法定相続分」はあくまでも目安であり、相続人の協議によって自由に決めることができます。
代償分割を行う際は、遺産を取得した相続人が代償金を支払う余力があるかどうか、不動産の評価額をどのように決めるかがポイントになります。
④共有分割(きょうゆうぶんかつ)とは
共有分割とは、不動産や有価証券などの遺産を相続人同士が共有する方法です。例えば、不動産を2人で1/2ずつ保有するといった状態で、これを「共有」「共同名義」などといいます。
共有分割は相続人間での不公平感がなく、分割しやすい点にメリットがあります。その一方で、固定資産税や建物の修繕費の支払い、共同名義人が亡くなった場合の相続など、その後の管理が何かと複雑になりやすい点に注意が必要です。
4.遺産分割の主な手順
遺産を分割する際は、一般的に以下の流れに沿って対応をします。
各手順の内容について詳しく解説します。
遺言書の有無を確認する
まずは、被相続人が遺言書を遺していないか確認しましょう。遺言書がある場合にはその内容に従って相続を行います。遺言書があっても、その種類によっては家庭裁判所での検認(遺言書の存在や内容を相続人に知らせ、偽造や変造を防止するための手続き)などの手続きが必要になることがあります。
相続財産を確認する
遺言書の有無が把握できたら、次にどんな遺産がどの程度あるのかチェックします。全体像を把握するために一覧表を作成するといいでしょう。現金や不動産といったプラスの財産はもちろん、ローンや未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。
相続人を確定する
遺産分割協議は相続人全員で行うものであるため、被相続人の戸籍を確認し、両親・配偶者・子どもなどを漏らさず確認します。「相続人は自分たち兄弟だけだから大丈夫」と思っていても、思わぬ相続人が判明するかもしれません。このように、戸籍を使って相続人を把握することを「相続人の確定」といいます。
遺言書がなく、遺産分割協議によって遺産の分け方を決めなくてはならない場合、居場所のわからない相続人がいても、相続人を探して連絡を取ることになります。
また遺言書があり、割合的包括受遺者がいる場合はその方も相続人と同一の権利義務を持つ人となります。
遺産分割協議を行う
相続人が確定できたら、遺産分割協議によって遺産の分け方について話し合います。
分け方を決定するためには相続人全員の同意が必要ですが、電話やテレビ電話で協議しても構いません。また、一度に相続人全員が協議できなくても、代表者Aさんと相続人Bさんが話し合ったのちに、代表者AさんとCさんで話し合い、同意を得るといった方法でも構いません。
遺産分割協議書を作成する
協議した内容は遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名および実印での捺印を行います。相続人が遠方に住んでいるなどの理由で、郵送で署名・実印を集めるといった手段をとることもあります。
遺産分割協議書は、不動産の相続登記(相続のために名義人を変更する手続き)を行う時に提出が必要です。また、話し合った内容に認識の相違がないことを確認し、トラブルを防ぐためにも役立つでしょう。
話がまとまらなければ調停・裁判へ
遺産分割協議で相続人全員が納得できれば円満に解決できますが、協議が決裂すると遺産分割調停の申し立てを行うことになります。できるだけ合意によって解決することを優先し、まずは遺産分割審判ではなく調停の申し立てを行うことが一般的です。
5.遺産分割調停の際に必要な書類や費用の目安
遺産分割調停の必要書類や費用の目安について紹介します。
遺産分割調停の際に用意が必要な書類
遺産分割調停に必要なのは、原則として以下の書類です。
- 申立書
- 事情説明書
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 戸籍(被相続人の出生時から死亡時までの連続した全戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本)
- 住民票又は戸籍附票(相続人全員分および被相続人分)
なお、相続人や遺産の状況などによってこれら以外の書類が必要になることもあります。その他、現預金の通帳や残高証明書、不動産評価額の査定書の写しなど、遺産に関する資料も必要です。
申し立てに必要な費用
申し立てには以下の費用が必要です。
- 収入印紙:被相続人1人につき1200円分
- 連絡用の郵便切手:当事者の人数分による
弁護士に依頼した際の費用
これまで紹介した内容は、弁護士に依頼しなくても行うことができます。しかし、弁護士をつけずに調停を行うと不利になる可能性が高いことから、できるだけ弁護士をつけることが望ましいと考えられています。
弁護士に遺産分割調停を依頼する際の費用の目安は、以下の通りです。
現在は、弁護士費用は各法律事務所が自由に決めることができるため、依頼前に確認するようにしましょう。
- 相談料:初回無料、もしくは30分で5000円程度
- 着手金:30万円程度~(遺産の額によって異なる)
- 報酬金:取得できた財産の4~16%程度
6.遺産分割終了後に遺言書が見つかった際の対応
遺言書は被相続人が遺した重要な意思であると捉えられるため、遺言書は法的に尊重されなくてはいけません。したがって、遺産分割協議の後であっても、遺言書が見つかった場合は、基本的にその内容が優先されます。
例外的に、遺言書で指定された遺産の受け取り手が相続人のみであり、遺言書で遺言執行者の指定がなく、かつ、相続人全員が合意している場合には、遺言書の内容とは異なる相続人が決定した遺産分割の内容を優先するケースも全くないわけではありません。
しかし、遺言書で指定された遺産の受け取り手に第三者の受遺者が含まれていた場合や、遺言執行者が指定されていた場合、また、遺言書での認知によって新たな相続人が生じたなどの場合は、遺産分割を最初からやり直す必要があります。
7.遺産分割におけるQ&A
遺産分割において疑問に感じやすいポイントを、Q&A形式で紹介します。
借金を相続したくない場合は?
遺産の相続には以下の3つのパターンがあります。
- 単純承認:被相続人の財産を引き継ぐこと
- 限定承認:被相続人の遺した財産の範囲内で借金も引き継ぐこと
- 相続放棄:全ての財産を放棄すること
借金を相続したくない場合には相続放棄をすることができますが、預貯金や不動産といった価値のあるものも全て放棄することになります。
限定承認は、相続対象の財産が、プラスの財産が多いのかマイナスの財産(債務)が多いのかわからない場合にプラスの遺産の限度で債務を負担するというものが限定承認です。
遺産分割協議書は必ず必要?
絶対に必要というわけではありませんが、協議の内容について明確にし、その後のトラブルを防ぐためにも、できるだけ作成したほうがいいでしょう。また、家や土地の遺産分割をするためには、相続登記のために遺産分割協議書が必要です。
既に財産を受け取っている相続人がいる場合は?
学費や婚姻費用、不動産の購入資金など、生前に被相続人から多額の財産を受け取っている相続人がいる場合、それを考慮して遺産を分けることが可能です。この制度を「特別受益」といい、不公平感を解消するために用いられます。
既に遺産を受け取っている相続人がいたら?
被相続人が亡くなる前に「私が死んだらあなたに◯◯をあげます」と約束しているケースも特別受益に該当します。この場合も、特別受益を受け取った相続人はその分を差し引いた額の遺産を取得することになります。
被相続人の世話をしていたら?
被相続人の財産の増加や維持に貢献した場合、遺産の取り分が多く認められる「寄与分」と呼ばれる制度があります。この寄与分が認められるのは、被相続人の事業の手伝いをしたり、仕事をやめて被相続人の看護を行ったりしたなどのケースです。
しかし、寄与分がいくらであるのか金銭的な価値にして計算するのは難しいため、財産の所有者に「確実に遺産を渡したい」と思う方は、遺言書を作成しておくことが推奨されます。
相続人と連絡が取れない時は?
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があり、全員の合意が得られないとその協議は無効になります。連絡が取れない相続人がいる場合にはその人を見つけ出さないといけません。
どうしても連絡が取れない場合は、「不在者財産管理人の選任の申し立て」「失踪宣告」といった方法によって対処します。また、遺産分割調停を申し立てると家庭裁判所から呼び出し状が送付されるため、他の相続人からの連絡を無視する人でも応じてくれるケースがあります。
不動産はどう分けたらいい?
不動産は以下のいずれかの方法で分割します。
- 現物分割:複数の不動産がある場合、そのままの形で分割する
- 換価分割:遺産を売却してそのお金を分割する
- 代償分割:一部の相続人が相続し、他の相続人に対して相続分に応じたお金を支払う
- 共有分割:1つの不動産を複数の相続人で共有する
遺言書に従いたくない時は?
遺言書の内容は重要度が高く尊重すべきものと考えられています。
が、もし、遺言書で指定された遺産の受け取り手が相続人だけであり、かつ、相続人全員が遺言書に従わない遺産分割の内容に合意している場合には、相続人が決定した分け方を優先することが可能です。なお、遺言書での認知によって新たな相続人が生じたなどのケースに関しては、遺産分割を最初からやり直す必要があります。
一方、もし、遺言書で指定された遺産の受け取り手に、第三者の受遺者が含まれている場合は、相続人全員に加えて、全ての受遺者の合意が必要となります。
第三者が遺産を受け取ることは可能?
遺言によって遺産を特定の誰かに譲ることを「遺贈」といい、親族でなくてもお世話になった人や支援したい団体などに遺贈することも可能です。ただし、一定の相続人に対して最低限の遺産である「遺留分」が認められており、遺留分侵害額請求を行うことで一部の取り分が与えられるケースもあります。
8.まとめ
遺言書がない場合には、誰がどの遺産をどんな割合で受け取るのか、相続人同士で決める必要があります。原則として遺産分割協議を行い、相続人全員が合意した内容で決定しますが、話がまとまらない場合には遺産分割調停・遺産分割審判に発展することもあります。
また、遺産の分割方法には現物分割・換価分割・代償分割・共有分割・指定分割の5つの方法があり、遺産の種類、相続人の状況などによって適した方法を選択します。遺産の相続は複雑であるため、手続きを適切に進めるといった目的で弁護士などの専門家に依頼するケースもあります。
遺産からの寄付の方法や注意点などをご説明した資料をご用意しています。
パンフレットに掲載されている内容は以下の通りです。(一部)
- 国境なき医師団とは?
- 遺贈寄付までの流れ
- 公正証書遺言とその作り方
- 自筆証書遺言とその書き方
- 遺贈Q&A
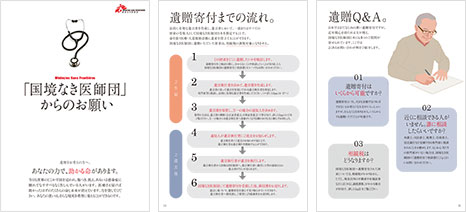
9.遺贈寄付に関するご相談
遺贈寄付の手続きは、誰にとってもはじめての体験。でも、相談できる人が身近にいない、という声も聞かれます。「国境なき医師団遺贈寄付ご相談窓口」には、幅広い知識と経験豊富な専任のスタッフがいます。遺言書の書き方から手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
国境なき医師団 遺贈寄付ご相談窓口
遺贈寄付専任スタッフがお手伝いします。
国境なき医師団には、幅広い知識と相談経験豊富な専任のスタッフがいます。
遺言書の書き方から、手続き上のことまで、遺贈のことなら何でも、お気軽にご相談ください。
-
電話03-5286-6430
- ※平日10:00~17:00 土日祝日年末年始休
-
E-Maillegacy@tokyo.msf.org

















三浦 美樹 司法書士 (一社)日本承継寄付協会 代表理事 司法書士法人東京さくら
代表理事 司法書士法人東京さくら 代表
代表
司法書士開業当初から、相続の専門家として多くの相続の支援を行う。誰もが最後の想いを残せる少額からの遺贈寄付にも力をいれている。
平成19年 司法書士試験合格
平成23年 チェスター司法書士事務所を開業
平成29年 さくら本郷司法書士事務所に名称変更
令和元年 一般社団法人承継寄付協会設立 代表理事就任
令和2年 司法書士法人東京さくらとして法人化