海外派遣スタッフ体験談
生まれる命と消えゆく命 小さくても、人間としての尊厳を忘れないケアを
2021年06月02日土岐 翠
- 職種
- 助産師マネジャー
- 活動地
- イエメン
- 活動期間
- 2020年10月~2021年4月
2回目の派遣で訪れたイエメン。前線近くの産科病院では、月に約500件のお産があり、たくさんの命が生まれる反面、助けられない命もあった。短い命と分かっていても、最後まで人として尊厳を持って精一杯ケアするように努めた。

銃声の聞こえる町で月に500件ものお産
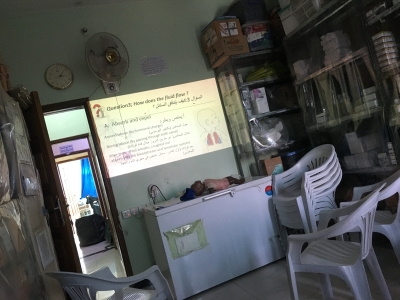
置く倉庫で行った © MSF
今回は2回目の派遣で、イエメンのタイズという街で活動しました。前線から10kmほどにある街で、銃声が聞こえることも多々ありました。国境なき医師団(MSF)がホテルをリノベーションした病院で、妊産婦と5歳未満の子どもを対象とした二次医療を行っていました。
担当業務は産科病棟のマネジメントで、産科スタッフは45人、分娩件数は月に450~550件程でした。具体的な業務は、病棟の回診、ベッドコントロール、産科スタッフのトレーニングの計画/実施、難しかった症例の振り返り、薬剤の在庫管理、プロトコールの作成などでした。
妊婦健診を受けられず、重症で運ばれてくる母子

2021年最初に生まれた双子の赤ちゃん© MSF
MSFの病院に来る約9割の妊婦さんが、貧困や医療アクセスの問題で妊婦健診を一度も受けられずに出産に至ります。血圧の管理などを含め、異常の早期発見や治療ができていない現状がありました。結果、合併症が進み母親が痙攣(けいれん)を何度も繰り返した状態で運ばれてくるなど深刻な状態であることが多く、赤ちゃんが出産前に亡くなるケースも多々ありました。
どんなにMSF病院のケアの質を上げても、地域の一次医療の質の改善や、コミュニティへの関わりを通して人びとに情報を提供していかないことには、根本的に問題は解決しません。今回のプロジェクトでは他病院、他NGOとの連携も強化して活動しました。
小さな赤ちゃん 短い命でも、人としての尊厳を忘れずにケア

かわいい毛布を着せて© MSF
前回のイラクでの活動と同様に、今回の派遣でも印象的だったことは、長く生きられない赤ちゃんへの対応です。1人の女性が10〜15回も妊娠をすることが当たり前のイエメンでは死産や新生児死亡がとても多く、その数はMSFの病院だけでも年間600件ほどに及びます。母親は出産後3時間程度の休息ですぐに帰宅し、家事や育児に戻ります。そのため、生まれた子が未熟児であったり、疾患などがあり長く生きられないと分かると、我が子を抱き上げることも、泣くことすらなく退院していく人がほとんどでした。その子にかける体力や気力はなく、泣いていられないのです。
現地ではその光景が当たり前で、“この子のことは忘れて、次の子を産めばいい“と言う声かけも良く聞かれました。私は、その時点でまだ生きている小さな子たちを“忘れていい“と思うことはできず、赤ちゃんであっても尊厳のある死を迎えられるよう現地の産科スタッフに指導をしてきました。
日本とは違い、紛争と貧困により限られた医療設備の中で諦めなければいけない命は数多くあります。それでも、その助けられない命が、どんなに小さく短い命であったとしても、ひとりの人間としてケアされて欲しいと願います。
寄り添い続けた心が伝わる

屋上から良く見ていた夕日 © MSF
妊娠中の赤ちゃんに重症の奇形があり、出産にリスクが伴うため、中絶を受けた19歳の女性がいました。母体を守るための中絶はイエメンでは合法ですが、宗教、文化的にあまり受け入れられていないこともあり、イエメン人のスタッフではなく、私が担当しました。中絶と言っても週数が中期にかかっていたため、その患者さんは出産と同じ経験をしなければなりませんでした。初めての経験に泣きながら怖がる彼女を前に、どうにか不安を和らげようと、つたないアラビア語で一生懸命コミュニケーションを取り、そばに寄り添いました。真夜中までかかりましたが、全ての処置は無事に終わりました。
言葉も通じない外国人に付き添われて不安だっただろうな、と思いながらも退院前に顔を見に行き、大丈夫?と声をかけると彼女は目を伏せ静かに頷いていました。入院中まともに私の顔すら見てくれなかった彼女でしたが、病室を後にしようとすると「シュクラン(ありがとう)」と小さな声が聞こえてきたのです。それは照れくさそうに笑う彼女からの感謝の言葉でした。
これから先、戦争の中で他の女性達同様に、彼女も妊娠、出産を繰り返していくのかもしれません。しかし、例えどんな状況であっても誰かにケアされていると感じてほしい、自分は女性として大切にされるべき存在だと知ってほしい。言葉は通じなくても、そんな想いが伝わってくれていたら、と願わずにはいられませんでした。
「なぜ行くのか」の問いに答え

今回のプロジェクトは紛争の前線に比較的近かったため、出発前は正直怖く、最後まで完遂できるか不安でした。しかし実際に現場に行ってみると、MSFの安全管理や情報共有は信頼のおけるもので、怖い思いをすることは一度もありませんでした。たとえ紛争中であってもそこには何十万人の人たちが冗談を言い合ったり、泣いたり笑ったり、普通に生活をしています。
「なぜそんな(危険な)ところに行くのか」と問われることも多々ありますが、今回の活動を通して、“そんなところ“だから行く必要があるということを痛感しました。一般の人が入れないところ、他の団体が活動できないところ、本当に医療を必要としている人たちはそこにいます。助けを必要としている人びとの元に医療を届ける、それがMSFの活動なのだと改めて納得しました。

助産師としてMSFで活動したい方は・・・
主な業務内容、応募条件など、
詳しくは『その他の職種』のページへ!







