「それでも、未来を信じて」村田慎二郎 連載
#1 “私たちの希望なのだから…”
2022.02.16

激しい空爆によって破壊されていく大都市アレッポ。被害があまりに大きく、援助活動の限界を感じていた村田は、ある患者の言葉に心を打たれます。
内戦下のシリアで国境なき医師団(MSF)の活動を率いた村田慎二郎が体験をつづる全8回の連載です。
(写真/内戦が続くシリアへ赴き、国境なき医師団の活動を統括した村田。現地の子どもたちとともに=2012年 ©MSF)
6年ほど前、もうすぐシリアでの任期を終え、日本へ帰る日も間近というときのことです。いつもだったら任務終了で得られる達成感もなく、私は身も心も疲れ果てていました。
活動地のアレッポでは、政府軍による容赦ない空爆や砲撃が続いていました。人口密集地でも、雨あられのような爆弾が降り注ぎ、女性や子どもを含め多くの人が無残に殺されていきました。反体制派が統制する地域では、学校やマーケット、病院といった一般市民の生活インフラでさえ、攻撃の標的となったのです。
病院が爆撃されたら、救えるはずの命もますます救えなくなってしまいます。

私たちのプロジェクトは、診療件数や患者数などを見れば、目標に十分達していました。けれども国境なき医師団は、当時この地域で活動する唯一の国際的な医療・人道援助団体。戦時の窮状で膨れ上がる一方の医療ニーズからすれば、自分たちのやっていることは「大海の一滴」に過ぎないのではないか──。私は虚無感に襲われるあまり、10年続けてきたこの仕事を辞めようとさえ思っていました。
ところが帰国直前、あるシリア人の患者さんとの出会いが、私の心を大きく揺さぶります。
「たる爆弾」を被弾し、片脚に重傷を負ったその患者さんは、病室でベッドに横たわっていました。爆撃で妻と子どもも亡くしていました。ちょうど同い年ぐらいの男性だったからでしょうか。疲れていた私はあろうことか、人道援助には限界がある、などと彼に愚痴をこぼしてしまったのです。
すると男性はこう言いました。
「そんなこと言わないでくれ。君たちは私たちの希望なのだから」(“Don't say that—you are our hope.”)
目が覚める思いでした。絶望の淵にあるはずの人に、逆に勇気づけられ、恥ずかしく感じただけではありません。戦争で自分の国の政府から攻撃され、国際社会からも見放されている人びとにとって、MSFの存在は“希望”になるのだと、初めて知らされたからです。
現地の活動責任者である私が気にしていたのは、「人口比に対する治療患者数」といった統計的な数字でした。でも、もう一歩深いところにも、MSFの活動には意義がある。彼がくれた言葉を何度も反すうしながら、成田空港に着く頃には、この仕事を続けていこうと固く心に決めていました。








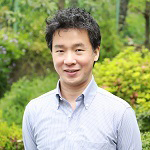
.jpg)