家族の声
家族の役割分担と周囲のサポート、みんなで実現した人道援助の道
-
中舘聡子(救急医)&寺尾英将さん(夫)
救急医の中舘聡子は高校生の頃、紛争地のことを伝えるニュースを見て、戦闘に巻き込まれて苦境にある人々を助けたいと、医師になって国境なき医師団に加わることを志した。国境なき医師団に入り、2024年に念願のイエメン派遣を果たした。
MSFを目指してからイエメンへの初回派遣にたどり着くまで、長く苦しかったと語る中舘は、MSFでの海外派遣をどう実現し、夫で整形外科医の寺尾英将さんはどのように見守り、支えたのだろうか。
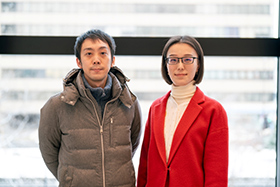
夫の寺尾英将さん(写真左)、中舘聡子(写真右)
Ⓒ Shun Nishimura/MSF
医師は一般的に、臨床研修後に大学の医局に入り病院に勤務し、キャリアを積み上げることが多い。しかし中舘は、医局に入らず独力で臨床経験を積む道を選んだ。
医局に所属すると勤務先の病院を紹介され、転勤を繰り返す。さまざまな経験を積み技量を高められるという点で、有利な面がある。一方で、医局の人事で病院に勤務した場合、個人の都合で長期の休みを取ることは難しい面がある。つまり、将来的なMSFでの活動に制約が出る可能性があると考えたからだという。
中舘は「救急専門医」を取得後、医師7年目でMSFに履歴書を提出した。その際にアドバイスを受けたのは、現場で幅広い年齢の患者に対応するため、小児救急の経験も必要だということだった。このため、東京都内に単身赴任して病院で小児救急を経験した。その傍ら、現場での活動に欠かせない英語学習にも励み、2023年にMSFの海外派遣スタッフに登録された。
念願の初回派遣は、2024年。内戦の続くイエメンで救急医として活動し、現地では小児や成人の救急医療に携わりながら、現場医師の教育にも関わった。

MSFを目指す妻、日本でキャリアを積む夫。互いの夢のため役割を分担
中舘聡子:MSFに入りたいという話は、ずっとしていました。
私が履歴書をMSFに出した時、夫も次年度から大学院に通う予定でした。期間は4年間。家族で話し合い、この期間に私はMSF参加に向けたキャリアアップに専念し、夫は大学院生活と家事育児をする、と役割分担をしました。家族のことは任せたぞ!って感じですね。このあと、小児科経験のため都内の病院で半年間の単身赴任をしました。
寺尾英将:妻がMSFで活動をすることは、正直僕の知らない世界の話という感じで想像ができませんでした。でも、やりたいことをやってみたらいいんじゃない、という気持ちでしたね。僕自身、大学院生活と家事育児の両立は思いのほか大変でしたね。
聡子:まだ子供が小さかったので、単身赴任の半年間という期間が長いと感じ、悩んだこともありました。でも最後は自分がやりたくて選んだ道だからと心を決めました。小児科を経験後、課題だった英語も何とかクリアしてMSFに登録された。
英将:この時は、お祝いでケーキを食べました。ただ、MSFの選考って様々な過程があって、何が終わったのかわかりにくかったのを覚えています。初回派遣の話が出てもビザや移動の問題など、実際の派遣になるまでに色々な事が起こり、本当に行けるのかなと思ったことも、何度かありましたね。
聡子:初回派遣まで、長期間待つことになりました。この期間は本当に長くて苦しかった。初回派遣となったイエメンの時は、ビザがなかなか下りず、出発が予定より1カ月遅れました。この間も不安でしたが、結果的に行けることになって本当に嬉しかった。
(注:海外派遣が決まった場合、MSF事務局の支援で派遣先のビザを取得することになるが、相手国側の状況などでビザ発行に時間がかかることもある)
英将:ここまでが長くいろいろあったので今回も行けない可能性もあるかも。駄目だった時の準備もしておこうと考えたりもしてましたね(笑)。
聡子:えっ、そんなことまで考えてたの(笑)!?

派遣中、さまざまな困難に直面。そんな時の家族の支え
聡子:イエメンでは、いろんな苦労がありました。
まずは言語。一緒に働くメンバーたちの訛りなどもあって、言っていることが聞き取りにくく苦労しました。仕事の内容は分かるのですが、日常会話になると本当に難しくって。言語的な問題に加えて安全のために外出がほとんど出来なかったこともあり、生活が日本と比べてガラッと変わりました。現地活動が始まってから6週間が経ち、予定していた短期休暇が諸事情で取れなくなったことも重なり、その時に肉体的にも精神的にもガクッと落ちてしまいました。
英将:イエメンの昼休みが日本の夕方だったので、その時間に電話でコミュニケーションをとっていました。当時を振り返ると、妻はかなりしんどそうでしたね。
聡子:日本語で話せることで本当に気持ちが楽になりました。夫も医師で仕事の相談もしていたので、頼りになりましたね。
英将:日本から遠く離れたイエメンだったので、話を聞くこと、僕にはそれくらいしかできないかなと思いました。辛かったら途中帰ってきてもいいんじゃない、と伝えたと思います。
聡子:そう言ってたかも。でも、それ(途中で帰ること)はないわ、と返したのも覚えています(笑)。
英将:確かに言ってたね(笑)。

経済が厳しく医療体制が整わないイエメンでの医療活動では、日本に比べれば少ない医療資源で、重症度の高い新生児や子どもの治療をすることになる。
交通事故で靴を履いていなかったため重傷を負い切断になったケースなど、経済状況が異なるがゆえに限界に直面したことも多かったという。仕事で緊張する場面が続くと体は疲れていても睡眠がとりにくくなることもあったが、チームメンバーに教えてもらった瞑想を取り入れ心身のリラックスを図ったりしたこと、そして何より家族との時間が、中舘の支えになったという。
周りに助けを求めることも、大切
聡子:約5カ月の活動を終えてイエメンから帰国しました。体力的にも精神的にも、かなり疲れていたと思います。帰国直後は、前々から楽しみに調べていたアフタヌーンティーに家族みんなで行きましたね。数週間の休暇を取ってから救急医の仕事に戻りました。
英将:もっと疲れているのかなと思っていましたが、思っていたより元気そうで安心しました。
聡子:MSFに入る前は、英語を勉強しなきゃと焦っていた部分もあるのかもしれません。帰国後は心に余裕ができたと思います。医学的な知識も語学的な部分でも現地活動で必要なことがつかめたような気がしています。子どもと離れていた時間が長かったので、子どもと過ごす時間が今はすごく楽しいですね。
英将:僕から見ても、心の余裕ができたと思います。以前は英語の勉強に焦っていたように見えました。時間的にも余裕ができたのではないでしょうか。
聡子:MSFに参加して本当によかったですし、「息長く続けたい」と思っています。今は夫の4年間の大学院も終わり、私も初回派遣に行けたので、私が子どもの送り迎えをするなど、今度は私の番だと思っています。
MSFに参加するから何かを犠牲にしなければいけない訳ではなく、それぞれの選択なんだと思います。MSFに対する思いを前々から周囲に伝えておくことも良いのではないかと。上手くいくことも、いかないことも、その過程を知ってもらうことでより応援してもらえるのではと思いますね。
英将:周りに助けを求めることが大切なんだなと、気が付くいいきっかけになりました。
職場だったり上司だったり、家族や子どもがいるとどうしても制限が出ますが、伝えることで、朝や夕方の仕事時間の融通を聞かせてくれたり、どうしてもいけない時に代わってもらえたり、夫婦で出来ないことを無理にやろうとしないくてもいいのかもしれませんね。僕たちの両親もその時々で助けてくれました。今は家事代行サービスなどの便利なサービスもありますしね。そういったものを活用するのもいいのかもしれません。

救急医としてMSFで活動したい方は……
主な業務内容、応募条件など、
詳しくは『救急医』のページへ!







